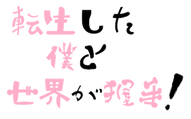ハロー、異世界
せめて、着替える時間が欲しかった――と思っても、今更地球へ戻ることも叶わない。
何故ならば、彼は次元移動の能力など持ち得なかったからだ。
仕方なくアニメTシャツのまま、付近を見渡してみる。
辺り一帯、緑に囲まれた森林に出たようだ。
町に出たいのだが、この辺の土地勘も、まるでない。
当たり前だ、ここは異世界なのだから。
彼が今までアニメで見てきた異世界トリップものだと、ここらで説明役のNPCが出てきてもいい頃なのだが……
しかし人影は、まるでない。全くの無人だ。
この時間に森へ遊びに来る人は、いないのであろうか?
誰もいないゴーストタウン、いやゴースト森林とは、何と寂しい風景か。
踊るなら今のうち、なんて言葉も彼の脳裏をよぎったりした。
だが、踊っている時に誰かと鉢合わせるのだけは回避せねば。恥ずかしい。
そもそも運動不足なので"踊る"という選択肢自体が、ありえなかった。
馬鹿なことを考えていないで、町を探そう。
森に出現してから、ゆうに十分経過して、ようやく可憐は歩き出す。
先ほども言ったが土地勘はゼロなので、とにかく適当に、太陽の方角へ。
可憐が町らしき集落へ辿り着けたのは、奇跡に近かった。
最後のほうは足が棒でフラフラになりながらも、無事にゴールインした。
いつもの自分なら五分と保たずに動けなくなっていたはずなのに。
世界一強い肉体とやらのおかげだろうか。一秒もダウンしなかったのは。
「あら。あらあら、まぁまぁ!」
唐突に甲高い声に叫ばれて、ふらふらの可憐が見たものは。
ロングスカートに、ふんわりしたブラウスを着た、目鼻の通った美人――
そこまでで。
あとは意識が、ぷっつり途切れた。
なにしろ、お腹が減りすぎて。
どれだけ強靱な肉体でも、これだけは、どうにもならない。
次に生まれ変わることがあれば、絶対にガス欠しない肉体がいいな。
そんなことを薄れゆく意識の中で、可憐は考えた……
可憐の意識が復活したのは、誰かの家のベッドの上であった。
鼻孔をくすぐる、美味しそうなスープの匂いで目覚めたのだ。
我ながら格好悪い出会いだったと思う。
いきなり倒れた自分を見て、あの美人は、さぞ困惑しただろう。
と、そこまで考えて。
可憐は、ハッとなって横を向いた。
さっきから、ずっと自分への視線を横手から感じていたのである。
「やっとお目覚めですね。ご機嫌いかが?」
にこっと微笑んだのは、なんと先ほどの美人ではないか。
では、この人が自分を助けてくれたのか?
いっちゃなんだが、可憐の体重は100kgを越えている。
一体どうやって担いできたのだ。
華奢に見えて腕力だけは強いといった理不尽なパワーをお持ちなのか?
混乱する可憐の耳に、もう一人の声が届く。
「おぅ、起きたか。あんた、町にやってくるなり倒れたそうだが」
男だ。
彼も、この家の住民だろうか。
美人が彼を振り向いて、微笑んだ。
「きっと、お腹がペコペコなんですわ。あなたに担がれている間も、グーグー鳴っておりましたもの」
穴があったら入りたいと、可憐は今ほど思ったことはない。
家を出る前に、たらふく何かを胃に入れておくべきだった。
「え、えっと……その、ありがとうございます……」
ひとまず彼らに助けられたのは事実なので、可憐はお礼を言っておいた。
男は気さくに笑い、「大したことァしてねーよ」と踵を返す。
「もうすぐ飯が出来る。一緒に食おうぜ」
「は、はい」
この上ご飯まで食べるのは申し訳ないのだが、断りづらい雰囲気でもある。
それに、ずっと自分を見つめている美人も気になっていた。
この二人は、どういう関係なのか。
普通に考えれば、夫婦なのだろうけど。
女性が町にいれば二度見してしまうぐらいの美人なのに対して、男は、いってしまえば、その辺にゴロゴロいそうな特色のない平凡な顔だ。
人間、顔じゃない。
と思っていても、やはり、そこは人並みに嫉妬してしまう可憐であった。
「あんた、旅人だろ。そのシャツ、あんたの故郷産か?可愛いな」
食卓に腰掛けるなり、男がニッカと笑って可憐に尋ねてくる。
「え、あ……まぁ、そんなところです……」
可憐は適当に言葉を濁し、頷いておく。
アニメのタイトルを出したって、彼には判るまい。他世界の文化など。
そういえば、先ほどからナチュラルに会話が成立しているのに気がついた。
異世界と聞いていたが、言葉が通じるのは有り難い。
言葉が通じなかったら、飯にもありつけなかったかもしれないのだ。
「いただきます」
両手を併せて、挨拶。
異世界の住民二人は不思議そうに可憐を見つめ、男が、また尋ねてくる。
「それも、あんたんとこの風習か?面白いねぇ、旅人さん。もし良かったら、あんたの故郷について色々と話を聞かせちゃくんねーか」
「え、あ……そんな、面白いところでもないですよ……」
いただきますと言っただけで面白がられるなんて、思ってもみなかった。
居心地の悪そうな可憐の態度に気づいたか、女性が男性を窘める。
「あなた、なんでも根掘り葉掘り聞くのは失礼ですわ。このかたは、疲れていらっしゃいますのよ。まずは、ゆっくり休ませてあげるべきではなくて?」
男が気さくタメグチ全開なのに、彼女は何故丁寧語なのか。
それも、気になる。
気になるが、しかし腹の虫も限界だ。
まずは、がっつり食べよう。
可憐はフォークを握りしめ、目の前の肉へ突き立てると、一枚まるっと自分の口に放り込み、くっちゃくっちゃと噛みしめる。
「ほぉ!一枚全部食うたぁ、よっぽど腹が減っていたと見える」
男が驚き、女性も口元に手をあてて目を丸くしている。
この一枚を全員で分ける手はずだったのだ――と可憐が気づいたのは、頬張った肉をゴクンと飲み込んでからだった。
「あ……す、すいません、つい……」
さすがに恥ずかしくなり赤面して俯く可憐に対し、彼らの反応は意外な事に、怒るでも、呆れるでも、そのどちらでもなかった。
「ははっ、気にすんな。腹が減って倒れたんだろ?そりゃあ、めいっぱい食べたくもなるよな。いいよ、いいよ、これも全部食え!あんたの為に作ったようなもんだ」
屈託なく男には馬鹿笑いされ、バンバン背中を叩かれながら、食卓に並んだ全ての料理を飲み込む可憐であった。
腹一杯食べて眠くなった可憐が豪快にベッドの上でイビキをかく間、家人の二人は、ひそひそと相談していた。
「ねぇ、あなた。これから、どうするつもりなの?あの旅人を」
「そりゃあ、決まっている。上手く丸め込んで、戦場へ送り出すのさ」
「やっぱり私が道案内役をしなければ、いけないのかしら……」
「そりゃそうだ。俺じゃ、あっちも警戒するだろ」
一応気さくな亭主を演じてみたけどな、と笑い、男が肩をすくめる。
女は眉間に皺を寄せて考え込んでいたが、やがて決断を下した。
「……そうね。仕方がないわね、皇帝のおふれですもの。あの人なら頑丈そうだし、前の旅人よりは長持ちしそうよね」
「あぁ。前の旅人は一週間で消息不明になったらしいからなぁ。今度こそ、長持ちする奴を送り込まないと、こっちの身もヤバイぜ」
なにやら不穏な相談をまとめると、二人は揃って奥の部屋を見やる。
そこでは可憐が何も知らず、スヤスヤと眠り込んでいるはずであった。
そう――誰かが、彼に入れ知恵でもしない限り。
「可憐、可憐。ねぇ、起きて?ボクだよ、君を召喚したマスターだ」
ゆっさゆっさと揺り起こされて、気持ちよく爆睡していた可憐は目を覚ます。
誰だ一体と不機嫌な目を向けてみれば、そこに立っていたのは小柄な少女だった。
まだこの家には住民がいたのか。
「可憐、このまま、この家にいると君は兵隊として差し出されちゃう。皇帝の思い通りに兵隊を増やしていちゃ駄目なんだ。このまま戦争を続けていたら、いつか世界も滅亡してしまうよ。可憐、ボクと一緒に、ここを抜けだそう。そして世界を平和にする旅へ出るんだ!」
おぉ。
これが噂に聞く、異世界転生トリップで必ず出てくる案内役のNPC。
またの名を、チュートリアルガールか。
腕を引っ張って、やたら急かしてくる少女の頭を可憐はナデナデした。
「ひっ!?な、何するのさ、セクハラ野郎!」
「よいではないか、よいではないか」
なにしろ寝ぼけているもんだから、可憐は半分夢の中だ。
「ん、もう。何言っているの?とにかくココを脱出するよ」
会話になっていない会話に焦れたか、少女が強硬手段を取ってきた。
いきなりドボッ!と可憐の脇腹に肘鉄を入れてきたのである。
これは痛い。目が覚める痛さだ。
「はぐっ!」と叫んだ可憐の口の中に、ぶっとい棒が差し込まれる。
それが何であるかを察する前に、もう一度鈍い痛みが土手っ腹を襲い、二度も腹を殴られてグッタリした可憐は誰かの肩に担がれる。
「――何者だ!待ちやがれ、そいつをどうするつもりだ!?」
意識を失う寸前に聞いたのは、優しい男性家人の叫び声であった。