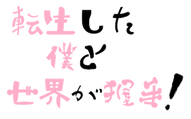不思議な世界の迷い人
意識が次第にはっきりしてきて、クラウンは身を起こす。周りは一面の草原だ。
遠目に森も見える。
その向こうには海が広がっているようだ。
一緒に入ったはずの可憐や他の仲間が側にいない。
ここは、どこだろう?
思案するクラウンの真横を誰かが走り抜けていき、ハッとなって見やれば、首に蝶ネクタイを巻いて黒のスーツに身を包んだ可憐が「あぁ忙しい、忙しい」と呪詛のように呟きながら走っていくところであった。
「待て、カレン!どこへ行くつもりだ」と呼び止めても、彼は立ち止まらずに走っていく。
時折、腕時計を見ては「あぁ、お茶会の時間に間に合わない」と呟いている。
お茶会とは何だ。
ここへは、試練の為に入ったのではなかったか。
――そうだ、エリーヌ!
彼女も近くには見当たらない。
ひとまず可憐を追いかけてクラウンも走っていけば、前方に見えてくるのはテーブルと椅子の一式で、テーブルを囲む形で四人ほど腰かけている。
あれが、お茶会なのだろうか。
しかし既に四脚とも埋まっていて、可憐の座る椅子がない。
と思っていたら可憐は「忙しい」を連呼しながらテーブルの脇を走り抜け、「待て、お茶会とは、これじゃないのか!?」と呼び止めて可憐を掴まえようとしたクラウンは、横から伸びてきた別の手に掴まえられて、椅子に無理矢理腰かけさせられた。
「さぁさ、楽しいお茶会の時間ですよ。お客様は椅子に腰かけて、お待ちください」
土瓶を頭にかぶっているのは誰であろう、アンナじゃないか。
傍らにはウサギの耳をつけたフォーリンや三角帽子をかぶったレン、ネズミの耳をつけたカリンがいて、四人とも、いつこのような珍妙な格好に着替えたのか。
「お茶会など、やっている場合か?エリーヌは見つけたのか。それにカレンも何処かへ走っていった、後を追わないと」
ごねるクラウンの目の前で、どぼどぼとグラスに注がれるのは青い液体だ。
青いお茶なんて見たことがないし、飲みたいとも思えない。
「取り出しましたるは異国の青い抹茶でございます〜。よく緑を青と呼ぶ輩がおりますが、これは正真正銘青の青!青い抹茶は健康にも美容にも良いと聞きます。さぁさ一気に飲み干してください?そーれ、イッキ、イッキ!」
アンナは、こちらの話が聞こえていないかのような振る舞いだ。
いや、このアンナは本当に本物のアンナなのか?
四人が幻想であるならば、早々に見破って本当の仲間たちを探さねばなるまい。
クラウンは椅子に腰かけて、順繰りに四人を見た。
正しくは、彼女達の魂を見た。色が示すのは、その者の本質だ。
本人か偽者かを見破る証にもなる。
じっと見やって、やがてクラウンは口の端を僅かにあげた。
「如何しました、お客様?青い抹茶はお気に召しませんでしたか」と尋ねてくるアンナへ、ぶっきらぼうに言い放つ。
「あぁ。見知らぬ奴の出す液体など、何が入っているか判ったものではないからな」
途端にフォーリンが「酷いですぅ!見知らぬ者だなんて、私達は仲間じゃなかったんですかぁ?」と大袈裟に騒ぎ出し、レンも「ポッと出の地味な私じゃ、地味すぎて記憶にも残らなかったって言うんですね。訴訟します!」と三角帽子をブンブン振り回してのキレっぷり。
それらを全て無視して、クラウンは告げる。
「お前らと仲間になった覚えはない。俺の知るフォーリンは薄桃色でアンナは茶色、レンは黒に近い灰色、カリンは無色だからな」
この場にいる四人は真っ黒な魂ばかりで、偽者なのは一目瞭然だ。
クラウンが答えた後、どこかでチッと舌打ちが聞こえ、お茶会の一式は瞬時にして消滅する。
アンナもフォーリンも全て消えてなくなり、テーブルのあった場所には扉が一枚出現していた。
この上なく怪しいし罠の香りがプンプンするが、闇雲に草原を歩き回っても仲間と出会える確率は限りなく低い。
どこかへ走り去っていった可憐も、偽者の可能性が高い。
躊躇したのも数秒で、クラウンは扉を開いて中を覗き込む。
扉の向こうは真っ暗だ。
意を決して一歩踏み込むと、目の前に広がるのは細い砂利道であった。
後ろを振り返っても砂利道が続いている。
先ほどまで一面草原だった場所は、扉と共に消えてしまった。
道なりに歩いていけば、誰かと合流できるかもしれない。
というより、歩く他なさそうだ。ここで延々立ちんぼしていたって、物事は進展しまい。
果てしなく地平線の彼方まで続く砂利道を歩いていくと、やがて前方に木々が見えてくる。
樹海、そう呼んでも差し支えないほどの広大な森林だ。
森へ辿り着くまでの間、一人も住民とすれ違わなかった。
まるで、この世界にいるのは自分一人だけと言わんばかりだ。
樹海の入口で立ち止まり、神経を集中させてみるが、生き物の気配は微塵も感じられず、クラウンは途方に暮れる。
一人で森に入って大丈夫なのか。
しかし、森に入るしか選択肢がないようにも思えてしまう。
砂利道は一本道、前にも後ろにも続いていたが、前は森が終着点だ。
後ろに戻ってみたら、何が見えてくるだろうか。
そう思って後ろを振り返り、そして、クラウンは驚いた。
道がない。
なくなっている。
背後に広がるのも木々で、無意識のうちに樹海へ入ってしまったのか――
だが、すぐにクラウンは脳裏に浮かんだ考えを否定する。
足は一歩も動かしていない。
だというのに、背景が森に切り替わってしまった。
相手の思うがままに操られている感覚を一身に受けるが、しかし帰り道がなくなってしまった以上は森の中を進むしかない。
道なき道、草の上を歩いていくクラウンへ、不意に横手から声をかけてくる者がいる。
「クラウンさん、みっけ!良かったぁ〜、樹海で遭難とかシャレになってませんでしたよ」
木々の向こうから顔を出したのは、ミラーだ。
魂は白に近い灰色の輝きを放っている。
間違いなく本人だ。
どこをどう歩いてきたのか、服や髪の毛には木の葉がいっぱいくっついていた。
「一人なのか?」と問えば、即座に「えぇ、一人っきりで森の中にいました。目が覚めたら、ここにいたんです」と答えが返ってくる。
「下手に動いたら遭難しちゃいそうだし、森にバケモノがいたら死んじゃいますし、どうしようって悩んでいたら足音が聞こえてきて……樹の後ろに隠れて覗いてみたんですけど、来たのがクラウンさんで安心しました」
「……俺が偽者だとは考えなかったのか?」とも尋ねれば、ミラーには首を傾げられた。
「え?偽者がいるんですか」
可憐の偽者と出くわしたのは自分だけなのか。
あの偽者は扉を抜けていかなかったから、まだ草原に残っているのかもしれない。
いずれにせよ、あの草原には戻れないのだから、確かめようがない。
可憐の偽者を追いかけるよりも、今はミラーと同行するのが大事だ。
「フォーリンやアンナの偽者がいた。だが、俺なら魔導の目で見極められる」
「それは心強いですね!」とミラーは素直に喜び、クラウンの横に並ぶ。
なんとはなしに、さくさく草の上を歩くうちに、ミラーがポツリと話し始める。
「……クラウンさんが来るまで、ずっと座って辺りを見ていたんですけど、この森って小動物が一匹もいないんですよね。昼間ですし、鳥がいてもおかしくない時間だと思うんですが」
「それは俺も感じていた」
ポツリと答え、クラウンは頭上を見やる。
やはり小動物の気配は一匹も感じられず、この世界に自分達以外の生き物は存在しないのか。
落胆した直後、前方に突如現れた気配へ向かって叫んでいた。
「そこにいるのは、誰だ!」
「怪しいものやおまへん」
どこか聞き慣れた方言が返ってきたかと思うと、声の主が目の前の大きな岩の上で、くるんと一回転。
そいつは丈の長い帽子をかぶったジャッカーと見せかけて、本人ではないのを強調するかのように、尻には長い尻尾を生やしていたし、頭には猫耳を生やしていた。
「ちょ、なっ、ね、猫っ?猫ジャッカーさん?可愛い!?」
動転するミラーを背に庇い、クラウンは誰何する。
「お前は誰だ。ジャッカーではないな」
「その通りや、ウチはジャッカーあらしまへん。アレや、えーと、なんやったっけ?そうそ、ジャッキーや。この狂った森での案内役と覚えてもらえば、おおきに〜」
どう見ても猫の格好をしたジャッカーだが、相手にはジャッキーだと名乗られて、おずおずとミラーも挨拶を返した。
「は……はじめまして?ミラーと申します。さっきまで森で迷子になって困っていたんですけど、あなたが案内して下さるんですか?」
「適応力の早いねーちゃん、ウチ大好きや。よろしゅうな」
キシシと笑みを浮かべて、ジャッキーなる者の視線がクラウンを捉える。
「そっちのイケメンにーちゃんは、なんてーの?名前」
クラウンは黙していたが、つんつんとミラーに何度も腕を突かれて、やがて溜息と共に名乗りを上げた。
「……クラウンだ。はぐれた仲間を探している」
ジャッキーの魂は緑色だ。
けして純粋とは言えないが、悪い色でもない。
緑の魂は判断力と適応力の高さを示している。
自ら案内役と名乗るぐらいだし、何が起きても対処できる冷静さを持っているのだろう。
「にーちゃん、ウチを信用してくれはったんやね。おーきに」
ニヤニヤ口角を歪めるジャッキーへ、クラウンは間髪入れずに質問で返す。
「それより狂った森だと言っていたな。どこが、どう狂っているんだ?」
対してジャッキーの回答は「ぜ〜〜んぶや」という要領を得ないもので、さらに聞き返そうとしたクラウン、それからミラーの耳にも謎の騒音が聞こえてくる。
大勢の人間が一斉にがなり立てながら、こちらへ向かってきているようだ。
「な、何なんですか!?」
慌てふためくミラーや身構えるクラウンにも、ジャッキーの警告が飛んだ。
「きよったで、さっそく狂った住民の出迎えや!えぇか、これから来る連中には何をされても一切抵抗するんやないで。一瞬でも敵意を向けたら最後、狂った女王様にギロチン処刑されてまうからなぁ」
「一体何が」と言いかけるミラーは、ドヤドヤ歩いてくる軍団に目を見張る。
樹木をなぎ倒して最短距離で向かってくるのは、四角い板に身を挟んだオッサン軍団だ。
手には槍や剣を持ち、どのオッサンも尋常ではないほど目をギラギラさせて興奮している。
あんなオッサンには、触られただけで悲鳴を上げてしまいそうだ。
と、考えている側からオッサンの一人に胸を両手でタッチされ、ミラーは思わず大声で「キャー!いやー!」と叫び、ジャッキーに腕を引っ張られる。
「あかんて!敵意もっちゃアウト言うたやろ!?」
「けど、この人、今、私の胸を思いっきり触ったんですよ!」
涙目でジャッキーへ訴えている間にも別のオッサンが背後から抱き着いてきて、「きゃあ、何!?」と振り返る暇もあらば、胸をモミモミされてミラーは滅茶苦茶に腕を振り回し、そのうちの何回かがオッサンの顎を直撃して束縛が緩んだのを幸いとし、腕の中を転がりぬけた。
「やだ、もう!セクハラすぎて抵抗しないとか無理!!」
オッサン軍団は突然のハレンチ行為で硬直するクラウンにも襲いかかり、キスされる寸前で我に返った「このッ!」というクラウンの気勢と共に、襲いかかったオッサンが股間を押さえて崩れ落ちる。
「あかんて!暴力いかんて!女王様にギロチンされたいんか!?」
ジャッキーが喚いているが、最早それどころではない。
オッサン軍団は次から次へとセクハラ行為を二人に仕掛けてきて、こんなものを許せる寛大さが二人にあるわけもなく、膝蹴りや肘鉄で撃退する。
手に持った槍や剣で攻撃されると思ったが、それはなく、セクハラ行為の一点張りだ。
倒しても倒してもオッサンの波は留まるところを知らず、このままでは、こちらの体力が先に尽きてしまう。
そうと判ったクラウンの判断は早く、「逃げるぞ、ミラー!」と彼女の腕を引っ掴み、勢いよく茂みに飛び込んだ。
「あぁ、あかんて!ウチが案内せなー、あんさんら迷子になってまう!」
叫ぶだけで追いかけようとはしてこないジャッキーを、その場に残し、あてもなく走り出す。
オッサン軍団は木も藪も関係なく一直線に薙ぎ倒して追いかけてきたが、蔦に掴まり、くるんっと樹木の上に登ったクラウンには追いつけず、そのまま一直線に暴走していき、姿が見えなくなったのを確認してから、ようやくホッとミラーが溜息をもらした。
「狂った森って、こういうことだったんでしょうかね……」
「たぶんな」と答え、クラウンは周囲を見渡す。
樹の上からだと、よく見える。
森を抜けた先には再び草原が広がっており、草原のど真ん中にはポツンと城が一つ建っている。
きっと城には、ジャッキーのいう女王様が住んでいるのだ。
極力近寄りたくない場所だが、もしかしたら仲間の誰かが囚われているかもしれない。
しかし城に立ち寄れば、先ほどのオッサン軍団にまた襲われる危険がある。
ちらっとミラーを一瞥し、クラウンは決断する。
「……あんたは、ここに残っていろ。俺が様子を見てくる」
途端、ミラーにはガシッとしがみつかれ、困惑するクラウンの耳に泣き言が流れてきた。
「勘弁してくださいよぉぉ。こんなところに一人でいて、さっきの軍団が戻ってきたら、私ひとりじゃ対処しきれませんよ!?できるだけ一緒に行動しましょう、クラウンさん一人で出歩いてピンチになっても困りますし!」
先ほどの軍団が木登りできるかと問われたら、非常に怪しいものがある。
しかしミラーの意見にも一理あり、一人でいくよりは二人のほうが予想外のアクシデントにも対応できよう。
彼女の乱れた衣服を直してやりながら、クラウンは前言撤回した。
「判った。では一緒に行こう。目的地は、あの城だ。女王がいるなら、この世界に関する詳しい情報が聞けるかもしれん」
ミラーは何度も「判りました。女王様との交渉は、私にも手伝わせて下さい」とコクコク頷いた後に、少々はにかんで付け足した。
「あ、それと……服、直して下さってありがとうございます」
クラウンは「礼を言うには及ばない」とだけ応え、彼女を抱えて飛び降りた。
答える直前、クラウンが目線を外してテレていたのを見逃すミラーではなかったのだが。