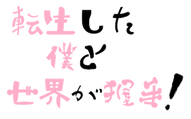役に立つのか、立たないのか
セルーンの統治者に会うには、池に落ちて扉の出現を待たなければいけない。だが鍵となる池は、どこに出現するかの具体的な情報が一切ない。
ここにきて、また手詰まりになってしまった。
これまでは何となく次の国へ行けば道が開かれていただけに、可憐は困惑する。
「池を探知できるような能力ってないのかなぁ」とミルに尋ねてみたが、残念ながら、そのようなチート能力はないようだ。
「闇雲に探しても見つかるもんでもないし、どうしよう」
腕を組んで考え込むミルに、アルマが思いつきを提案する。
「あたし達が空から探すってのは、どぉ?」
しかし「出撃以外での発進は禁じられている」と即座に刃司令の駄目出しが入り、ぷぅっと頬を膨らます。
「そんなこと言ってたら、何もできないじゃない」
「ですが、空から探すのも闇雲です。具体案が決まってからじゃないと、意味がありません」
エリーヌも止めに入り、不意に懐からごそごそと取り出したのは四角い箱、通信機であった。
「クルズ全域であれば、騎士団に命じて探すことも可能です」
さすが王女――と言いたいところだが、それにもミルがマッタをかける。
「池を探すのはいいけど、今のボクらだけで難題を突破できるかな?」
「まだ仲間が必要だと?」と質問に質問で返してきた刃へ頷くと、仁礼尼へ振り返った。
「挑戦権は一回きりだったよな。失敗したら、サイサンダラの平和は永遠に訪れないってわけだ。ここは慎重にやらないと」
「だから、そんなこと言ってたら堂々巡りで何もできないでしょ!」
アルマが混ぜっ返し、話し合いはまとまりそうもない。
それまでずっと黙していたユンが、ぽつりと呟いた。
「……アナゼリア大尉……そうだ、海軍を上手く利用すれば」
「え?何か思いついたの、ユン兄」
ナナに促され、ユンが言うには。
アナゼリア大尉率いるセルーン海軍第七艦隊は、ユン達第九小隊の引き渡しをワの海軍に持ちかけていた。
首都襲撃でうやむやになりかけていたが、これを上手く利用できないものだろうか。
具体的に言えとキースにも急かされ、ユンは真顔で言い放つ。
「大尉に、もう一度会いに行く。行くのは俺一人で充分だ」
「え、えぇぇーーー!?」と驚く仲間を、ぐるり見渡し、付け足した。
「交渉は得意ではない、が……大尉は俺が相手であれば、話を聞いてくれるだろう」
「それは、劇薬を盛る前までの彼女ではなくて?」と突っ込んできたのはセツナで、眉間に皺を寄せて大尉の今を案じる。
「目覚めた彼女は、自分に何が起きたのかを他の者たちから教えられているはずよ。劇薬を盛った犯人が誰なのかもね」
「薬を作ったのはキースでしょ、ならユン兄は悪くないんじゃないの」などとナナは気楽に言っているが、自分がアナゼリアだったら間違いなくユンを恨むと可憐にだって簡単に思いつく。
なにしろ眠りにつく直前、会った相手はユン一人だけなのだから。
ワに引き渡しを持ちかけたのだって、反逆者を処刑したいからに決まっている。
絶対に会うべきではない。第七艦隊とは。
再び、うーんと考え込む一同だが、ミルが、あっと顔をあげる。
「どうしたんだ?」と尋ねる可憐へ「地形を把握できる能力があるのを思い出したんだ」と答えると、こちらも荷物から通信機を取り出した。
「お母さんが前に言っていたんだけどね。具体的に何が出来て何が出来ない能力なのか、聞いてみる」
「あ、それならウチも聞いた事あるで」と、通信にストップをかけたのはジャッカーだ。
「ダラーの地上絵やったかいな、そんな名前の能力やろ?ミルはんのお母はんが言うとったのは。自分が見た事も行った事もない場所の地図を描くことができる能力や」
「予知夢みたいなもん?」と可憐が尋ねるのには否定して、「ちゃうちゃう、そやな、予知やのうて千里眼の地図版みたいなもんや」とジャッカーは笑った。
そんな便利能力がある人なら是非とも仲間に加えたいが、はたして誰が持っているのか。
これまでの仲間の能力でさえも完全把握していない可憐である。
「せやな、この際やから改めて自己紹介も兼ねて、全員の能力確認といきまひょか」
「ひとまず今日は、ここに泊まらせてもらおうよ」
またまた思いつき全開なアルマの提案に、仁礼尼は、にっこり微笑んだ。
「えぇ、どうぞ、部屋は幾つでも空いております」
「え、ホントにいいの?」「わぁ〜言ってみて良かった!」と喜ぶバトローダー達を眼窩に収め、シズルがひそひそと刃へ相談を持ちかける。
「とうとう上層部への連絡もなしの無断外泊になっちまったぜ?宗像のやつが怒り狂って変な真似してねぇといいんだが」
「大丈夫だ、副指令がいる限り」と答え、刃は、ちらりと幼馴染を上目遣いに見上げた。
「それよりも外泊は久しぶりだ。学生以来じゃないか?おまけに布団を寄せあっての雑魚寝は初めてだ……ワクワクしてきたぞ」
なにを暢気なと半分呆れつつ、嬉しそうな刃を見るのも久しぶりだとシズルは独り言ちた。
夜、布団を部屋いっぱいに並べての全員雑魚寝で雑談会が始まった。
「まずは、この俺、名はキースだ、よろしくな。そして俺の能力だが」
トップを切ったのは、キースだ。
「御霊の冠だ。これは初対面の異性を魅了する、まさに俺の為にあるかのような能力でな」
「え、そんな能力持っていたんですか。全然知りませんでした」と突っ込んだのは、同じ小隊所属のレンだ。
「あたしも知らなかった」とナナも呟き、何度も首を傾げる。
「だって、あたしもレンも全然魅力を感じないんだけど、変態眼鏡から」
「ま、まぁ、確かに初めて見た時は格好いいなと思いましたよ、キースさんのこと」
却って、この旅で新しく知りあったアンナが気を遣ってしまう有様だ。
「そうだね。カレンさんやクラウンさんと先に会っていなかったら、そう思ったかも」
ミラーも華麗な追い打ちコンボでトドメを差し、改めて全員へ頭を下げる。
「私はミラーと申します。考えてみれば後から仲間に入った皆さんには、きちんと挨拶していませんでしたね。能力は先ほども言いましたが算術の山、多少計算が上手い程度の大したことのないものです」
その横で「あたしはアンナ、能力は憧憬の泉です。頭で妄想した景色や人物を、絵で的確に表すことができます」とアンナも軽く会釈した。
「それ、実際にやってみてよ。見てみたい!」
ケイのリクエストに頷くと、しばらくボ〜ッと虚空を見つめて何か考えた後、おもむろにカバンの中から紙とペンを取り出して、さらさらと絵を描き始める。
ややあって「じゃ〜ん、クラウンさん!」と彼女が見せてくれた絵は、非常に完成度の高い写生であった。
「うっわ、うま!どんなのかと思っていたけど想像以上にウマッ!」
日頃SNSで上手なイラストを見続けていた可憐も唸るほど、会心の出来だ。
いわゆるアニメ絵ではなく美術絵なのだが、写真を紙に貼りつけたのではないかと見間違うぐらい、隣に座る本人とそっくりだ。
人物画で、このクオリティーなら風景画も息を呑む出来上がりになるのであろう。
この能力が可憐にあったら、きっと美術はオール五が取れたし、絵で人気者にもなれた。
凡人と異なる特殊な能力は永遠の憧れである。
可憐のように、何の取り柄も持たないキモオタだった男には。
フフーン!と鼻息荒くご満悦なアンナの横で、フォーリンが、ひょこんと頭を下げる。
「え、えぇと、フォーリンと申します……能力は、その、えっと、アンナさんと比べてしまうと大したものでは……」
消え入りかけた自己紹介へ、意地悪そうな顔を浮かべたミルが突っ込んでくる。
「きみが持つ大層な能力なら、一つあるじゃないか。何をやっても駄目っていう天性のマイナス能力が」
あまりにあまりな嫌味には「カレンの前でフォーリンを虐めるのは感心しない」と小声で諫めて、クラウンが全員を見渡した。
「クラウンだ。能力は魔導の目。魂を色で感じ取る」
「その能力、ボクとフォーリンも持っているからね」
ミルが続け、やや柔軟に表情を和らげる。
「フォーリン、魔導の目は混戦で仲間を見極めるのに役立つ優秀な能力なんだぞ。あまり謙遜するんじゃない、もっと自信を持てよな」
「は、はい、あの……ごめんなさい、ミル。気を遣わせてしまって」
ウルウル潤んだ眼で見つめてくるフォーリンを疎ましげに手で払いのける仕草をして、「ボクはミル。大魔法使いエリザベートの子供だ。能力は魔導の目と、天満の花。召喚獣を呼び出してほしかったら、ボクに頼むといい」とミルが胸を張る。
そこへ「魔法なら私も得意手だ」と、ドラストが鼻を鳴らして割り込んでくる。
「我が名はドラスト、得意魔術は氷だ。能力は天満の花、連発には自信がある」
「そうですね。山中では、大変お世話になりました」
深々とお辞儀して、レンが微笑む。
「私はレン。能力は、ちょっと判らないですね。これまでの人生で、能力を使わなければいけないほどの危機に陥ったこともなければ、閃いた事もありませんので」
「あたしも〜」とナナが手をあげ、小首を傾げてみせる。
「能力って突然見えたりするもんなの?なんか、それもすごいね。あたしはナナ。レンと同じ時期に海兵へ入隊したんだ。あたし達、親友なの!」
「そしてナナたんは俺の嫁である」
満面の笑みを湛えて呟くキースなど、誰も気にも留めていない。
「私はセーラ、この可愛いプリティボーイはラブユーカネジョーくんよ。私達、恋人なの!」
突然の素っ頓狂な自己紹介には、鼻をほじって半分寝ていたカネジョーも驚きだ。
「誰が誰の恋人だ!?そんなんじゃねーだろ、俺達は!あぁ、俺はカネジョー、能力は知らねぇ。あいつらと一緒で死ぬほど酷い目に遭った事がねーんでな」
「そうねぇ、セルーン海軍は強すぎるものねぇ。ま、うちの小隊は、そもそも戦場に出ていなかったけれど」と頷き、セーラは遮られた自己紹介の続きを話す。
「私の能力は精練の指といって、道具や武器を整備するのに必要な手先の器用さを高める能力よ。まぁ海軍の武器は布で拭くだけのお手軽整備だったから、この能力が役に立つのは、いつも実家で故障ばかりするパン焼き機を修理する時ぐらいだったわね」
見ようによっては凄く役立ちそうな能力なのに、地味な使われ方をしていたようだ。
ちらとユンを見てから、セツナが語り出す。
「私はセツナ。セルーン海軍では医者を勤めていました。能力は開眼の刃。体内の悪い部分を切開後、肉眼で捉えます」
「それで医者に?」とエリーヌに尋ねられ、頷いた。
「えぇ。能力は役に立てる場面で使ってこそのものです」
「あらぁ、私の能力だってパン好きな母には役に立つものだったわよ」
スネるセーラへも頷いてみせ、セツナは最後に嫌味で締めくくる。
「えぇ、お母様は貴方に多大な感謝をしているでしょう。何の役にも立たない変態眼鏡の犯罪能力とは大違いだわ」
「犯罪能力だと?聞き捨てならんな。俺の能力は、世界の女性を幸せにできる美しさだぞ」
斜め上に憤慨するキースの弁を遮ったのは、第九小隊隊長のユンだ。
「……ユン。能力は鉄の爪」
ふいっと視線を逸らして布団の中へ潜り込もうとするのはキースが阻止し、続きを促す。
「オイ、説明が終わってないぞ。言いたくないなら俺が代わりに説明してやろうか?」
そこへ、目を爛々と輝かせてアンナが突撃した。
「キースさんとユンさんって仲良しですね!もしかして親友ですか?デキちゃってますか!?」
「ちょ、ちょっとやめなよ、また例の悪い癖?」と横で止めるミラーを無視して、なおも鼻息荒く食いこんでゆく。
「それともナナちゃんレンちゃんと一緒で、同期の桜ってやつですか?苦難を一緒に乗り越えたり!?そして芽生える友情、恋に発展……!あぁ、インテリ眼鏡×コミュ障イケメン、イケるイケる、どっちもイケメン万歳だわ!」
一人で盛り上がりまくる腐女子には、さしもの女性好きなキースでもドン引きだ。
「いやいや、なんだ恋って。ただの友人だ、なぁユン?」
ユンを見やれば布団をすっぽりかぶって、聞こえないフリの狸寝入りをしているではないか。
仕方なく、キースがユンの能力を説明した。
「鉄の爪は何事にも動じない鋼鉄の神経とでも言えばいいのか、要は鈍感だな」
「失礼ね!ユン兄は、冷静沈着っていうのよ」
ナナが抗議し、傍らではレンが何度も頷いて深い同意を示す。
「なるほど、冷静沈着ねぇ。そうと言えない事もないか」
寝たふりを続けるユンをチラ見し、シズルは苦笑する。
「俺はシズル、水門の防人の末裔だ。能力は水の崎守。こいつは俺んちで先祖代々受け継がれる能力でな、本来なら海軍が適しているんだろうが……まぁ、俺もヤイバも軍人になる予定は全くなかったからなぁ」
「で、どんな能力なんだ?」と尋ねる可憐へは片目をつぶって答えた。
「水を操る。小さい頃ちょっとだけ使ってみたら、水門をぶっ壊しちまった。それ以来、親父にゃ禁止されちまって全然使っていねぇ」
水門を守る一族なのに、水門を壊すとは何事か。
大吾が禁止にするのも当然だ。
当時を思い出したのか、くすっと小さく笑った刃が、自分も名乗りを上げる。
「自分……いえ、ここではプライベートとして話しましょう。俺の名前は白羽刃、ワ国第38小隊空撃部隊の司令官を勤めています」
「俺なんだ!?一人称ッ」と可憐には大袈裟に驚かれ、少し身を引き刃も首を傾げてみせる。
「おかしい、でしょうか……?」
「うーん、俺より私とか僕ってほうが似合いそう、イメージ的に」
可憐の答えへ、最も激しく賛同したのはアンナであった。
「判ります、それ!一人称僕で、ですますのほうが妖艶っぽくてイメージ通り!」
「よ、妖艶、ですか……」
本人は滅茶苦茶引いてしまったようだが、しかしキモオタ視点で見て、ここは譲れない。
刃は色白で、ほっそりスレンダーだ。やはり僕か私が妥当であろう。
一人称俺には粗野な印象がつきまとう。シズルなんかが良い例だ。
といったどうでもいい可憐の主張は根こそぎ無視して、ドラストが刃に能力の有無を尋ねる。
「それより司令官殿は、如何なる能力をお持ちなんだ?」
「プライベートでは刃とお呼びください」と断ってから、刃が答える。
「我が能力は、神楽の剣と申します。如何なるものも刃物の一振りで斬り離す――しかし実際の効力に関しては保証しかねます。なにしろ、一度も発動させたことがありませんので」
ならば何故自分にあるのを知っているのかと問えば、母からの聞き伝えだという。
「どのみち、お前じゃ無理じゃないか?その細腕で剣をふるうのは無理だろ」
キースのバッサリな突っ込みには、本人も即座に頷いた。
「はい。俺は生身で戦えませんし、今後も戦う予定がありません。無用の能力ですね」
「能力があっても、必ず使い道があるとは限らんもんなぁ」とジャッカーも憐憫の色を見せ、かと思えば笑顔になって皆の顔を眺めまわす。
「その点、ウチはツイてたわー。使い道の多い能力で!ウチはジャッカー、解除士や。鷹の指で何でもホホイと解除したるでぇ」
解除の腕前は、以前クラウンの呪いを解くので見せてもらっている。
ミルとジャッカーとドラストは、ツイていたクチだ。
元々有能な能力の上、フルに活用できる道が見えていたのだから。
「アルマは、どんな能力なん?」とジャッカーに話をふられ、アルマはキョトンと切り返す。
「あたし達?あるのかな、生まれつきの能力なんて」
彼女達はバトローダー、人工生命体だ。
人工生命体やモンスターにもチートな能力は、あるんだろうか?
可憐がそうした疑問を口にする前に、シズルが、ばっさり否定する。
「あーバトローダーには、ねーぞ。つけてないからな、初期設定で」
「じゃあ、作る時につけたら、つくん?」との追加質問にも、首をひねって応答した。
「どうだろうなぁ。つけたってのを聞いた事ねーや。ローダーは全部無理なんじゃねぇか?」
サイサンダラに産まれても、人工生命体はチートな能力を持たざる種族のようだ。
神社の外で寝ているであろうクラマラスに想いを馳せ、彼女達には空を飛べる能力があるのにな、と可憐は考える。
これで全員分、能力は把握できただろうか。
ひーふーみーと指を折り、可憐は最後の一人に尋ねてみる。
「エリーヌ、きみの能力は?」
「はい」と嬉しそうに両手を併せて、彼女が答えた。
「私の名はエリーヌ。能力は、高嶺の花でございます」
「うわ、見たまんま!」と思わず突っ込む庶民の反応を一通り楽しみ、能力の概要を説明する。
「高嶺の花は殺傷力絶大です。えぇ、簡素に説明いたしますと、身にまとわりつく害虫を軒並み排除する能力です」
その場にいた庶民が想定していた能力とは、およそかすりもしない内容だった――