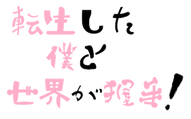セルーン王打倒計画
悪政であろうと皇帝を崇拝するクルズ国民とは異なり、セルーンは皇帝と国民の連帯感が薄い。いや、薄いという表現は的確ではない。
頭を押さえつけられて無理やり従わされている、と言ったほうが正しかろう。
それもそのはず、セルーンの国王は人間ではなかった。
何千もの知識を抱え込んだデータベース――すなわち、機械が今のセルーンを収めている。
といったことを海兵レンの口から聞かされて、ミルもエリーヌも呆気に取られたのであった。
長年戦っていた相手が、自分の意志で戦っていなかったとは驚きだ。
クルズは皇帝が操られていた時期は徴兵制になっていたが、洗脳が解けた後は志願制に戻った。
軍人志願者は皆、自分の意志で戦争へ身を投げていた。
"戦いたくない奴は辺境に引っ越せ"とは国民の間で伝わる、暗黙の了解だ。
「へぇ〜セルーン王は機械やったん。なら、誰かしら壊せそうなもんやけど」
ジャッカーの楽観的思考に、第九小隊女子の面々が総勢で突っ込みを入れる。
「えー?壊すなんて無理だよ〜」
「セキュリティの問題もあるし、軍人が二十四時間体制で警備しているのよ」
「それに、故障しても自己再生しますからね……」
他国民が思いつくぐらいだから、戦争反対派が過去何度か挑戦したのは想像も容易い。
それでも変えられなかったというのは、そういうことだ。誰も破壊に成功しなかった。
「機械を動かすには、電源がいるんだったよね……エネルギー源は、何?」と、ミル。
「あ、それも自家発電で補っています。弱点がないのですよ、我らが王には」
レンがあっさり答え、この分だと恐らく停電が起きても何らかの処理が施されていよう。
魔法が効くとも思えない。イルミを相手に戦うのであれば、魔法対策は完璧なはずだ。
まぁ、ミル達は王様本体を退治しにきたのではないから、戦う必要などない。
要は王様と直接話が出来れば、いいのだ。
王様と直接の取次ぎを行っているのは誰かとミルが問うと、それにもレンが即答する。
「総務大臣です。ですが、彼と会えるのは軍隊の最高司令官だけですよ?今は他国との交流も断絶していますし」
「総務大臣が死んだら、誰も取りつげなくなっちゃうんですか?」とは、アンナの質問だ。
「次の大臣が決まるまでは、そうなるかしらね……」
首を傾げるセーラの発言には、レンがフォローを入れた。
「ですが次の大臣は翌日決まりますから、何も問題ありません。我らが王の采配に、抜かりはないのですよ」
人事管理も完璧だ。完璧に機械によって管理された社会、それがセルーン国である。
「機械に手足として使われている事に不満を持つ国民は、一人もいないのかな……」
ポツリと呟いたミルに、すかさず反応してきたのはナナだ。
「そんなことない、皆、不満だらけだよ!けどねぇ、逆らったら死刑だし、そもそも逆らう意味もないよね」
「どうして?」とミルが聞き返せば、少女兵は首を傾げて、こんなことを言う。
「逆らうデメリットのほうが大きいもん。従っていれば、とりあえず生活は確保できるし、職も斡旋してもらえるし。一応、進学か就職かの選択も発生するし?」
即死と比べれば、従うほうがマシなのだろう。
しかし宛がわれた環境で管理される生活は、本当に生きていると呼べるのか?
比較的自由のあるクルズから来た者には、どうしても、そこが理解できない。
たとえ皇帝に管理された環境だとしても、クルズ国民には選択肢があった。
戦争に参加するか否かの自由が。
話を聞く限り、セルーン国民には自由がない。
進学を選んだとしても、いずれは戦地に駆り出される。
選択の余地がない。
だが産まれた時から、そうした環境下にあったのでは、逆らう気も起きまい。
機械に飼いならされたセルーン国民を味方につけるには、どうすればよいのか。
「逆らったら死刑になるって、死刑を実際に執行するのは誰の役目なんですか?」
アンナの質問に、「そりゃあもちろん、下級の兵士だよ」とナナが答える。
「ほたら、その下級兵士が反逆起こしたら、誰も処刑できなくなるん?」
ジャッカーの思いつきに、セーラがハッとした表情を浮かべた。
「そうね、言われてみれば、その通りだわ。なんて斬新なアイディアなの……さすが他国民、侮れないわね!」
ジャッカーが言わずとも、誰かしら思いついていそうな発想である。
さらにミラーが突っ込んだ質問をした。
「下級兵士とは、陸軍のですか?」
「えぇ、そうですね。大抵は陸軍が命じられます」と、レン。
ジャッカーを一瞥し、すぐにミラーへ視線を戻すと、小声で囁いた。
「実は、過去に下級兵士が反乱を起こした事件なら一度あったんですよ。結局は鎮圧されてしまったんですが……」
同志討ちで潰されたか。
ならば同志討ちが出来ないほど反乱分子を増やしてしまえば、どうなるか?
ミルの提案にレンは考え考え、慎重に答えを出す。
「反逆するメリットがないと難しいですね。支配を逃れて自由になるというだけじゃ、具体的ではありません。自由になった先の生活も保障されませんと、動く兵士は少ないでしょう」
「じゃあ結局、セルーンの民が自由になるには国王を倒さないと無理ってこと?」
「そうなりますね。しかし国王を倒す、ですか……我々は考えもしませんでした。いやぁ、さすがは他国民」
レンにも唸られ、ミルは口を尖らせる。
「そこまで呆れるほど荒唐無稽な話かな?だって国王が機械である以上は、人の手で作られたモノだろ。なら、必ず弱点が存在するはずだよ」
「そうねぇ」と腕を組み、セーラが思いつきを述べる。
「国王に会えるのは総務大臣だけ。なら、その大臣にとって成り代われば、国王に会えないこともないわよね」
「問題は、どうやってセキュリティーを突破するかです」と、レン。
意外や、レンもセーラもミルの話題に乗っかっている。
先ほどまで無理を連呼していたはずなのに、どうした風の吹き回しか。
不思議に思ってフォーリンが二人に尋ねると。
「いや、ねぇ」とレンはミルをチラ見して、何度か感心したように頷く。
「本当にできるんでしたら、乗っかってみるのも悪くないかなぁと思いまして。だって、このまま戦争に参加して死ぬよりはマシじゃないですか?あなた方の理想とする未来に乗っかったほうが」
ただし完全に協力するには具体案が必要だとも言われ、フォーリンはミルを見た。
「とのことですが、具体的な案は、あるのですか?ミル」
答えたのはミルではない。ミラーだ。
「一時的にでも、セキュリティーを外すことが可能ならば……軍人の壁も大臣の認証も突破して、国王に会うことが可能になるはずです」
「認証がいるなんて言ってなかったのに、よく判りましたね?」
驚くレンに、さして驚くことじゃないとミラーは断り、首をふる。
「相手は機械ですから。人物を認識するのに認証が必要かと推理したまでです」
「軍人の壁は、偉い人が間違った情報を流せば、混乱させられるよね……」
ぽつりとナナが呟き、「うちの家名が役に立つんじゃないかな?」と持ちかけてくる。
難色を示したのは、レンだ。
「ナナの家名?つまり、それは隊長の名を汚すということになりますが……」
ナナの家の立場を利用するのは、ユンの立場を脅かす事にもなる。
レンがユンを心配して、意義を申し立てるのは当然だ。
だがナナは、気楽に笑って「ユン兄も抱き込んじゃうから問題ないよ」等と言う。
思わずレンは突っ込んだ。
「問題しかないですよ!反逆が失敗した場合、その後の生活はどうなると思って」
「成功させるんです」と遮ったのは、それまで黙っていたエリーヌだ。
「自由とは、誰かに与えられるのを待つものではありません。自ら勝ち取りにいかなければ、得られないものです」
「さっすが王女様、かっこいいー!」
ナナがはしゃぎ、レンはというと、傍らでポカンとしている。
セーラは思考が早くも反逆計画に移ったのか、ぶつぶつと独り言を呟いた。
「そうね、この反逆を成功させるには機械に強くて、法を犯しても良心が痛まない奴を見つけておかないと」
「そういう人、一人知ってるよ!」と、ナナ。
セーラも「たぶん私の知る奴と、あなたの知る人は同一人物だと思うわ」と笑った。
ややあって、我に返ったレンが騒ぎ出す。
「つ、つまり……第九小隊だけで、王家に反逆すると――?む、無理です、そんなの」
だがミラーは、あっさり彼女の不安を打ち消しにかかる。
「いくら兵が守っているといっても、王の寝室まで守っているわけじゃない。まずは王様の側に近づく方法を考えましょう。やりもしないでムリムリ騒いでいるよりは、建設的かと思いますが?」
男性陣も引き込んで、具体的な作戦を立てよう。
そう言ってミルが話を締め、その日は落ち着かない夜を過ごしたレンであった……