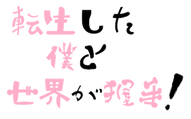セルーンのヒミツ
可憐の動きを封じてまでミルがやろうとしていたのは、実に単純な策だった。単純であるがゆえに、第九小隊唯一の良心でさえも、その魂胆には気づけなかった。
セルーン海軍がエリーヌ姫を捕えてから、二日目の朝を迎えた。
朝食の支度を済ませ、レンがナナを呼ぶ。
「ナナ、捕虜の様子は、どうでしたか?昨日と変わりありませんか」
「うん」と頷き、ナナはレンの作った朝食を覗き込む。
自分達の飯ではない。捕虜用の飯だ。
昨夜の飯は好評であった。いつもより薄味にしたのが、良かったようだ。
今日のメニューは固焼きのパンと野菜サラダの付けあわせで、飲み物はミルク。
「王女様って言うからさ。もっと豪勢なご飯じゃないとヤダー!って騒ぐかと思ったのに、案外素直だよね」
ナナの正直な感想に、レンも頷いた。
「数人の部下のみをつれて他国へ出かけるぐらいですからね。ただの温室育ちな、お姫様ではないんでしょう」
掴まった直後は抗議していたようだが、テントに連れてこられてからのエリーヌ姫は大人しく。
出された食事に一切文句を言わず、「美味しい」と喜んでもいた。
もっと我が儘を言われるんじゃないかと危惧していた第九小隊の面々は、些か拍子抜けした。
王女の同行者にしても、そうだ。
撃沈させられた当日だけだ、文句を言っていたのは。
こちらの他愛ない雑談には素直に乗ってくれたし、飯もトイレも誘導に従っている。
脱走する素振りすら見せていない。もう諦めてしまったのだろうか?
「あの子、ミルって言ったっけ。あんな小さいのに我慢できるんだね。えらいよね」
「若くして王女おつきの召喚師ですからね……我々とは精神面が違うんでしょう」
捕虜にしては大人し過ぎる――
それが、レンの抱いた印象だ。
だが何かを企むにしても、たった数人で何ができる?
周り一帯軍人に囲まれた場所であれば、大人しくなるのも当然か。
王女を筆頭に、幼子の召喚師と行商人。
国王お抱えだった元暗殺者に、イルミ国の魔術兵までいる。あとは民間人が数名。
セルーンへ攻め込むにしても、休戦交渉するにしても、おかしなメンツだ。
「そもそも、彼らは何しにセルーンへ来たんでしょう?」
首を傾げる親友に、ナナが適当な思いつきを答える。
「やっぱり、お忍び旅行じゃないの?」
「お忍びなら、優秀な騎士を一人二人連れてきそうなものですが……」
「元暗殺者の人が、護衛代わりなんじゃないの?」とナナは、さほど問題にもしていない。
彼女を見ていると、自分の考えは杞憂ではないかとレンも思ってしまいたくなる。
しかし自分までもが能天気な思考でいたら、大事な局面で失態を犯しかねない。
一瞬でも浮かびかけた気楽な発想を、レンは頭を振って追い払う。
「まぁ、疑問に思ったなら、本人達へ直接聞いてみればいいんですよね」
隣の友に言うでもなく小さく呟くと、レンは朝食の乗ったワゴンを押していった。
ミル達の囚われているテントは、第九小隊の管理する駐屯地内に張られている。
セルーン海軍は各小隊ごとに駐屯地を持っており、数が若いほど最前線に近い。
駐屯地と言っても、二階建ての四角い建物が一軒あるだけの質素な敷地だ。
ただし必要最低限の一式設備は用意されているから、生活には困らない。
セルーン領土内には、こうした駐屯地が無数にあるから、他国の侵入を寄せつけない。
空以外は完璧な防壁になっている――はずであった。
国民の士気を考えなければ。
「着替えは、お済みになりましたか?朝御飯の時間ですよ〜」
ぽむぽむとテントの布がノックされ、続けてワゴンを押した海兵が入ってくる。
「すみません、お忙しいのに私達の食事を作っていただいて」
捕虜に労われ、レンは苦笑交じりに手を振った。
「いえいえ、これも仕事のうちですから……」
「でも、これって自腹なんやろ?」と突っ込んだ質問をしてきたのはジャッカーだ。
行商人と名乗られたが、捕まえた時点では何も売り物を持っていなかった。
「ま、まぁ、そうですね。でも、あとで軍に経費を請求しますから」
言い訳する横から、今度はアンナとミラーの質問が飛んでくる。
この二人は町人同士の幼馴染で、海軍が沈めた船の持ち主という話であった。
「昨日のフルーツサラダも美味しかったけど、今日の野菜サラダも彩り豊かですね!これは、どなたか菜園を?」
「あ、いえ、近くに農家があるんですよ。そこで買い取らせていただいています」
答えながらレンは全員の顔を見渡した。
初日は落ち着かない様子だった少女達も、二日目の今日は、すっかり元気だ。
捕虜になったというのに、他国の生活への興味が勝っているようでもある。
「駐屯地の近くに農家が?危なくないですか」とのアンナの問いには、笑って否定した。
「ここは内地ですからね。ここまで攻め込まれるようだったら、セルーンは、とうに滅びています」
第九小隊の駐屯地は、国境沿いの最前線から遠く離れた内陸にある。
一般民に近く、軍人の少ない地域だ。
ここいらの民の暮らしは、けして豊かではない。
豊かではないからこそ近辺に駐屯地を作り、軍が民の作った農作物等を購入する。
そうやって無理やり民の不満を押さえつけているような面もあった。
もし、セルーンの民が他国の兵士に貧乏であると知られたならば、そこを付け入れられるのではないかという懸念はレンにもある。
幸い内陸奥地まで攻め込まれたことは、ここ数十年間一度もないので大丈夫であろう。
ほとんどの軍人が出稼ぎ勢で構成されているのも、不安の種だ。
ユン隊長のように、生まれついての上流貴族なんてのは全体の一割にも満たない。
「ところで、ボクたちの旅の目的を、まだ話してなかったよね?」
ミルの言葉で、レンは、ハッと我に返る。
「そうですね。大尉からは密入国目的ではないかと伺っておりますが、密入国するにしても目的が、おありなんですよね?」
「密入国っていうか、入国手続きを出す前に問答無用で沈没させられたんだけど……」
ぽつりとレンの間違いを訂正してから、改めてミルは彼女を見つめる。
「ボクたちはエリーヌ姫のつきそいで、他国の情勢を見て回る旅の途中だったんだ」
「他国の、情勢……ですか?しかし」
それにしては騎士の一人も連れていないのは不用心ではないか。
そう続ける前に、エリーヌ本人からも注釈が入る。
「私達は戦争を仕掛けに来たのではありません。戦争で苦しむ民の様子を、実際にこの目で確かめたかったのです」
「確かめて、どうするおつもりだったのですか?」
レンの後から入ってきたセーラに尋ねられて、エリーヌは、きっぱり答えた。
「苦しむ人がいるようでしたら、この戦争を止めようと。そう思ったのです」
ぽかんとなって、ナナもレンもセーラも次の言葉が、すぐには出てこなかった。
何百年と続いた戦争を、たった数人で終わらせるつもりだったって?
荒唐無稽、世間知らずにも程がある。できるわけがない。
そういやナナがカレンの紹介を促した時にも、彼を救世主だと呼んでいた。
戦争を終わらせるために現れた勇者だと。
あれは本気で言っていたのか。
箱入りお姫様の思いつきに同行させられる、おつきの人々も大変だ。
レンが笑い飛ばそうとした矢先、ナナからは素っ頓狂な言葉が飛び出した。
「すごい!本当にできるとしたら、もう戦わなくて済むんですよね!」
「え?ちょ、ナナ?」
慌ててレンがナナを見やる横では、セーラも感嘆の溜息をついている。
「自分が生きている時代で平和になるなんて、考えもしなかったわ……平和になったら、そうね、まずはカネジョーくんとデートしなくっちゃ!」
さすが我らが第九小隊、自分以外おつむのネジがぶっ飛んでいるのは伊達じゃない。
などと明後日の方向に妙な感心をしている場合でもない。
なんとしたことか、二人とも姫の夢想に心を動かされまくっているではないか。
「できっこないですよ!」
否定の言葉がレンの口を飛び出し、ミルには「なんで?」と首を傾げられる。
「だ、だって戦争を止めるには王様と会談しなきゃいけないんですよ?各国の王に会談を申し込むにしたって、糸口がなければ不可能です」
「クルズとイルミは既に終戦条例を結ぶ手筈が済んでおります」と、エリーヌ。
再び、えっ?となるレンを置き去りに、凛とした表情で語りだす。
「戦争を終結させる――それを無謀だと思われるのは、ごもっともです。ですが私達はイルミ国の最長老とお会いして、休戦の約束までこぎつけました。次はセルーンの王に面会するため、こちらの海域に来たのです。扱いが捕虜となっても構いません。王に会えるというのであれば」
「かっこいい……!」
「各国を行き来できるようになったら、カネジョーくんをお洒落させなきゃ。あぁん、カネジョーくんは、どんなお洋服が似合うのかしら?」
ナナは姫に羨望の瞳を向けているし、セーラはセーラで己の妄想に突っ走っている。
ますます劣勢を感じながら、レンは切り札を持ち出した。
「これまでが上手くいったからって、セルーンでも上手くいくとは思わないでください!最長老様には会えたとしても、セルーン王は、そうはいかないんですっ」
「けど、セルーンの王様だってイルミの最長老と同じ一人の人間だろ?なら、捕虜として会った際に話をすれば」
茶々を入れるミルをも遮って、大声で言い切った。
「違います!セルーンの王は、人じゃない。城全体が王なんです!セルーン王とはデータバンクなんです、だから誰も意見を挟むことは許されない!!」
これは一般民も与り知らぬ、軍人だけが知る極秘事項だ。
セルーンは全てを機械が支配する。
大臣も艦隊長も、所詮は国家のネジの一本に過ぎない。
セルーンに人間の意志なんてものは、存在しない。
国民の自由があると思っていた、民間人だった頃の自分が懐かしい。
軍人になって真実を知り、打ちのめされた。希望を持つ心も、いつしか忘れた。
ここまで話すつもりは、なかった。
どんな話題を振られても、無難な雑談だけに留めておくつもりだった。
なのに他国のお姫様から与太話を聞かされて、思わず冷静さを欠いてしまった。
と、レンが気づいたのは、自ら情報を叫んだ後だった――