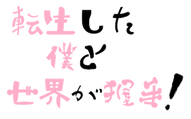セルーン内情
「へぇークルズでは、今そのようなデザインが流行っているんですか!」一方、女子組のテントでは。
レンとナナに囲まれて、フォーリンやミラーが世間話で盛り上がっていた。
ドラスト以外は全員クルズ人であることや、モンスターが同行していた件も話し済みである。
イルミの海を越える場面では、盛大にテントが盛り上がった。
諸国漫遊冒険物語の殆どを彼女達に話したのは、少しでも情を傾けさせる策だ。
軍人でもなく捕虜でもなく、一介の人間としての視線で、こちらを見て欲しい。
戦争は国vs国ではなく民間人同士の無駄な傷つけあいである。それを自覚して欲しいのだ。
軍人として教育されてきた相手に、それを思い出させるのは厳しいかな?
と、最初はミル自身も自分の立てた策に自信がなかったのだが。
意外や、レンやセーラは最初から戦争反対派であった。
聞けば、レンの片眼は戦争で潰されたのだという。
彼女の住む街がイルミ国の空軍に爆撃され、家ごと吹っ飛んだ際に負傷した。
では、イルミ国には深い憎悪があるのでは?と尋ねたフォーリンへ、彼女は首を真横に振る。
そして、はっきり言ったのだ。
悪いのは戦争ではなく、憎悪を他国に向けさせようとする自国だと。
そこまで判っているのに、何故軍人になったのか。
ミルの問いにもレンは答えた。
それはそれとして、生活資金を稼がないと人は生きていけないのだ。
つまりは、貧しい出生が故の出稼ぎ勢である。
がっぽり大金が入ったら、いつでも軍人を辞められるということだ。
ナナは義兄ユンが軍人になったので、後追いで軍人になった。
セーラの入隊理由は、出稼ぎでも追っかけでもない。
地元が戦地に近かった為、ほぼ強制で入隊させられたそうだ。
この中で愛国心のある人〜!とアンナが問えば、ドラスト以外手を挙げないのにはエリーヌも苦笑せざるをえなかった。
今は全ての国が崩壊している。民間人に愛されていないのでは。
「いいわねぇ、クルズは。セルーンはパターン化しちゃっているのがネックよね」
はぁ、と溜息をついてセーラがアンナやミラーの服装を見やる。
どちらも、まったくの普段着だ。とりたてて珍しいファッションでもない。
アンナは黒いTシャツに皮の長ズボン。ミラーは灰色のブラウスにスカート。
それでもセーラは羨ましげに二人を眺め、もう一度溜息をついた。
「そんなにバリエが少ないんですか?セルーンのオシャレ事情」
アンナの質問に、セーラは若い二人にも同意を求める。
「少ないなんてもんじゃないわよ、ねぇ」
「そうですねぇ」と答えたのは、レン。
「限られたパターンの中で、如何に着回すかが鍵となっています」
「具体的には、どういった?」とのミラーの質問には、ナナが答える。
「パターン柄っていうの?柄物が多くて、今、あなた達が着ているような無地が、ほとんどないのよね。だから、組み合わせで誤魔化すしかないってわけ」
戦争で各国の流通が滞っている以上、何もかもを自給自足しなければいけない。
軍事面で見れば、セルーンは機械文化に優れていた。
しかし民間面で見ると、自国の娯楽生産は他三つより遥かに及ばない。
クルズはファッションと家具の生産が娯楽文化の要だ。
「クルズがイルミに攻め込む前は、貿易での流通もあったと聞く」とは、ドラスト。
「全ての元凶は、クルズだったんですよね……」
しみじみレンが言い、一時場の雰囲気が暗くなったりもしたけれど、すぐにキャピキャピは復活し、次の話題に移った。
「ねぇねぇ、ところで、あの二人だけど」
ナナに聞かれて「あの二人?」とフォーリンが首を傾げる。
「そ、あの二人。どっちが誰のカレシなの?」
間髪入れず、エリーヌは答えた。
「クラウンは私の婿です!」
「あ、この人の言うことは半分以上妄想なので、気にしないで下さいねー」
小さな声でアンナが突っ込み、レンやナナはウンウンと頷く。
それでも興味は尽きないのか「クラウンって、どっち?」と、またまたナナが尋ね、「黒服の人が、そうですよ〜」とフォーリンが教えてあげる。
「ちなみに、天使の微笑みを携えた人は我らの救世主、可憐さんです!」
えらい自信満々なフォーリンの態度には驚いたのか、「大きく出ましたね」と呟いたレンが「救世主とは?」と尋ねてくる。
「救世主は救世主です。異世界から現れて、この戦争を終わらせにやってきた勇者様なので〜す!」
これには「異世界から!?」と女性三人も声を揃えて驚愕し、改めてミルを眺める。
ミルが召喚師だというのは、一番最初の自己紹介で教えてある。
従って、可憐を召喚したのがミルだという結論に行き着くのは容易いであろう。
「そうだよ、可憐はボクが召喚した」と、当のミルが言う。
続く「なお、彼は誰のカレシでもないから」との一言には、フォーリンがエッとなった。
一番最初の約束で、可憐の恋人になると許可したのは、ミル本人なのに。
もう忘れてしまったのだろうか。或いは最初から、どうでもよかった?
「えっ、そうなの?まぁ、そうだよね……イケメンも度が過ぎると、ちょっと手を出しづらいよね」
納得したのか何度も頷くナナに、アンナも同意する。
「あの隣に並べるのは、どんな美女だって話ですよね」
「民間レベルでいうと、うちの隊長やキースさん、クラウンさんあたりが標準的なイケメンでしょうか。あれなら手を出しても大丈夫と思えます」
滅茶滅茶冷静にレンが評価し、セーラは、というと。
「あらぁ、何言っているのよ。うちのイケメンナンバーワンボーイはカネジョーくんでしょぉ?あっ、貴方たち、だからといって手出しは無用よ?彼は私のコ・イ・ビ・トだからっ」
バチーン☆とウィンクをかましての斜め上発言にはエリーヌ達もポカンとなり、小声でレンが突っ込んだ。
「この人の言うことも妄言なので、信じないで下さいね〜」
「コイバナもエェけど」と、水を差してきたのはジャッカーだ。
「ウチは現状について、もっと教えてほしいわぁ」
「いいよ。何が知りたいの?」
気さくなナナの態度に、ジャッカーも思いきって尋ねてみる。
「もし、人質作戦が効かなかったら。ウチら魚の餌になってしまうん?」
一瞬にして場は静まりかえった。
「あ、あれ?ウチ、聞いちゃいけないこと聞いてしもうたん!?」
慌てるジャッカーを置き去りに、軍人三人は寄り集まってヒソヒソ内緒話をしていたが、やがてレンが笑顔で、こちらを振り返って結論を述べた。
「それは、我々下っ端兵士には与り知らぬ情報です。上層部から第七艦隊へ連絡が来るのは、早くても一ヶ月以上かかるでしょうし」
これまで現実と向き合いたくなくて、雑談をふっていたのだ。
せめて人質の皆さんには、空気を読んで欲しかった。
交渉が失敗したら?そりゃ勿論、全員を見せしめで殺さなくてはなるまい。
軍人が相手なら、遠慮なく戦えるし処刑も可能だ。
しかし無抵抗な民間人を殺すのは、さすがにレンもナナも良心が痛む。
どうせ処刑を任されるのも、我が第九小隊であろうし。あの陰湿大尉の考えそうな事だ。
できることなら逃がしてやりたいし、交渉も成功して欲しい――
チラッチラと無言のSOSをナナが出しているのに、ミルは気づく。
第九小隊はポンコツ小隊。
なるほど、確かに軍人としてみればポンコツ以外の何者でもない。
だが、今はそのポンコツっぷりが有り難い。
もう少し情で揺さぶりをかければ、こちらの言いなりになってくれそうだ。
腹黒い算段を胸に秘め、ここから先は自分も態度を変えてみようとミルは考えた。