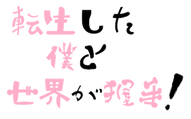上には上の
仁礼尼に「これを」と差し出された書簡を受け取り、エリーヌは頷いた。「白羽様への紹介状、書いていただきましてありがとうございます」
「いえ、この程度でしたら、いつでもお手伝いできましょう。ですが、ワ国との停戦に持ち込んだとしても……セルーンへの再入国の目処は、立っておりますのでしょうか?」
「なんでボク達がセルーンに一度入ったと知って、って、そうか!」
疑問を自ら途中で打ち消し、ミルが仁礼尼へ確認を取る。
「君は、ワ国の海軍とも繋がっているんだね」
「いいえ、そうではありません」と首を振り、仁礼尼が全員の顔を見渡す。
「ここはワの国、最果ての土地――ですが、ワ国の官営塔でもございます。情報は全て我が元に集められ、首都や軍部へ送られます」
「どうやって?」と可憐が尋ねると、仁礼尼は微笑み真っ向から彼を見据えた。
「私の持つ――銅間の鏡、で以て」
直後、ミルが「銅間の鏡だってぇ!?」と大声を出すもんだから、可憐は驚いた。
「知っているのか?ミル」と促せば、彼女は興奮気味に頷く。
「百年に一人しか生まれてこないっていう、幻の能力だよ!ホントにいたんだ……ずっと眉唾、御伽噺かと思っていたっ」
鷹の指もレア能力だと聞かされていたが、上には上がいるのか。
どんな能力なのかとミルに尋ねるまでもなく、本人が語りだす。
「私の目は、未来を視ます。過去を視ます。遠く離れた土地で、何が起きたのかを知り得ます」
要は千里眼と予知夢の合体技か。
かつて前の世界にいた頃は、可憐も予知夢に憧れたものだ。
なんせ未来を予知できれば、競馬も宝くじも当て放題。大金持ちルート確定だ。
過去も見えるそうだが、終わってしまった出来事を知って何になるのであろう。
大事なのは未来と今だ。
ばっさり切り捨てた可憐とは異なり、キースやユンは「過去もだと!?」と驚いている。
「なら、もしやセルーン王の正体や弱点も知っているのか?」
「もちろん」と頷き、仁礼尼の視線が挑戦的にキースへ向けられる。
「弱点は、あります。ですが、少人数で解決できるものではないでしょう。あなた方に勝算は、あるのですか?四国全てが停戦せねば覇王戦争も終わりませぬよ」
「私達は」と膝を進めて、エリーヌが断言する。
「セルーン王を武力で倒したいのではありません。あくまでも平和的な話し合いによる、和解での停戦を望みます」
「いや、それは無理だと言っただろう」とキースが横から口を挟み、仁礼尼も同意するかのように頷き、しかし、こうも言った。
「王と直接の対話は、そこな眼鏡男の言う通り無理でしょう。ですが、相手が王でなければ――?」
「おい、誰が眼鏡男だ!」
憤慨するキースなど全くスルーして、エリーヌが尋ね返す。
「大臣ならびに臣下の方々とであれば、対話が可能だと?」
仁礼尼は首を真横に否定する。
「いいえ、いいえ。それも一つの和解ではありますが、違います」
なかなか進まない会話に焦れて、ジャッカーも口を挟んでくる。
「王じゃなくて臣下でもなかったら、誰と話すっちゅうねん。そもそも王以外と話すんは無意味やろ。国の一番偉い奴と」
ジャッカーの言葉は「あっ!」と叫んだミラーによって中断される。
「な、なんやねん」と慌てる彼女を押しのける形で、ミラーが仁礼尼に尋ねた。
「もしかして、セルーンの国を治めているのは王ではないんですか!?」
この結論には全員が、ぶったまげだ。
だって、それだと第九小隊ことセルーン国民の話と大きく食い違ってしまう。
セルーンは何をするにも何を決めるにも、王の承諾を必要とする。
実質上、王が国を治めているも同然ではないか。
だが、仁礼尼はパンと手を打ち頷いた。やっと正解だとでもいうように。
「えぇ、その通り。機械王はフェイク、偽りの王でございます」
「はいぃぃ〜〜?」と声の裏返るセルーン国民を置き去りに。
過去も遠くの出来事も見える仁礼尼の言うことには。
機械王が生み出されたのは、国民の意思をコントロールする為だった。
覇王戦争でセルーンが勝者となるには、機械武器の量産だけでは足りない。
戦争で勝ち残るには、国民一人一人の強靭な意志力が最後にモノを言う。
民を団結させるためのシンボルが、"機械王"という存在であった。
全ての決断を機械王に委ねる。という情報を巧みに流し、民を支配下に置いた。
機械王は同時に首都のセキュリティーも兼ね、兵士の反乱を防いだ。
王の判断は、王自身の人工知能によるものだ。
だが、その王を管理する者がいる。
その者と交渉すれば、或いはセルーンを停戦に追い込めるやもしれない。
「ひ、一人なのですか?その管理者とやらは」
驚くレンに、仁礼尼が頷く。
「セルーンを陰で牛耳るのは、何百年もの長い月日を生き抜いてきた者です。その者を説得できれば、王も会談に応じるでしょう」
「何百年も生きてきたって、モンスターかなんかですか?」とはアンナの問いに。
「いいえ」と首を真横に振り、仁礼尼が、じっと可憐を見つめる。
首を傾げる彼へ向けて、はっきりと答えを口にした。
「その者は、モンスターではありません。異世界人……とでも呼ぶのが、相応しいでしょう」
――一時の静寂を置いて。
座は皆の驚きで、けたたましくも騒がしくなる。
「い、異世界人だとぉ!?カレン以外にもいたのか、異世界人が!」
「だから人間の召喚は危険だと言ったのだ!カレンは無害だが、他はそうと限らんと」
「てか機械王が作り出されたのって、覇王戦争の序盤でしたよね!?そんな昔から異世界人が潜伏してたんですか、我が国には!」
「ミル、君は知らなかったのか!?」と泡食った可憐に尋ねられ、ミルは勢いよく首を振る。
「知るわけないだろ、他国の召喚状況なんか!」
しかし思い起こせば異世界へ渡る魔法を編み出したのは、セルーンの魔術師ではなかったか。
そう、次元移動魔法ポトなんとかだ。
それを使えば異世界人の一人や二人、召喚できてもおかしくないのでは?
可憐が尋ねると、「あぁ、ポトファトラムか。よく覚えていたね」とミルには褒められる。
「待て、大魔導士エクソスラムの逸話なら私も知っているが――」
二人の会話を聞いていたのか、ドラストが眉を顰める。
「だが、彼が活躍した時期はサイサンダラ歴178年だぞ?戦争が始まったばかりの頃には生まれてもいない」
「え」と固まる可憐を横目に、ミルも深々頷いた。
覇王戦争が始まったのは、今より二百年前のこと。
すなわちサイサンダラ歴35年だ。178年は割と近代であろう。
「え〜。ミルの言い方だと、すっごい昔みたいだったから」
ひとまず自分の勘違いをミルのせいにしておくと、可憐は改めて考え込む。
「ボクは大昔だとは、一言も言わなかっただろ!」と怒る彼女など、そっちのけで。
管理者たる異世界人は、どうやってサイサンダラへやってきたのか。
ちらっと仁礼尼を見やると、彼女は無言で微笑んでいる。
心なしか、うずうずしているようでもあったので、可憐は水を誘ってみた。
「仁礼尼さん、君は答えを知ってるの?」
「もちろんです。私は過去も未来も視える尼ですよ」
勢いで答えてから、あっと口元に手をやるも、じろっと皆に睨まれて、しょぼしょぼ回答を口にした。
「できましたら皆様、自力で答えに辿り着いてほしかったのですけれど……そうですね。正解を申しましょう。大魔導士エクソスラムは次元移動の魔法を編み出しました。次元移動とは世界を跨ぐものだと捉えられがちですが、彼の編み出したポトファトラムは、それだけの魔法ではありませんでした。彼の魔法は、過去や未来へも移動の出来る代物だったのです」
またしても、座にいた全員が「ど、どええぇぇぇええぇ!?」と大合唱。
構わず仁礼尼は、話を続ける。
「エクソスラムは異世界に飛んで一人の若者をつれてくると、今度はサイサンダラの過去へ飛びました。そして、こう言い渡したのです。セルーンの国を滅ぼしてはならぬ。何年かけても必ずセルーン国を勝利に導くのが、お前の使命だぞ――と」
「え、えぇぇ?しかし、そうなると管理者が機械王を作ったということに?で、でも、その前の過去では機械王は、なかったということになりますよね。あ、あれ??いや、違うか、エクソスラムが未来を書き換えたってこと?」
頭を抱えるレンを見て、可憐は唐突に閃いた。
これは、タイムパラドックスというやつに違いない。
昔、何かの漫画、ドラえもんだったかで読んだ記憶がある。
未来の人間が過去を改変してしまうと矛盾が起きて、パラレルワールドが発生する。
では今、可憐がいるのはパラレルサイサンダラなのか。
しかし、それを今、この場で考えるのは無駄だ。
パラレルであろうと何だろうと、今いる世界を平和にするのが自分達の目的なのだから。
「参考までに、そのエクソスラムさんは今でも生きてるの?」
存命ならば厄介だ。世界を平和にした後で、また改変されかねない。
仮にパラレルが発生したとして、元の世界がどうなるのかは可憐にも想像つかない。
ミルが手をパタパタ振って「もう死んでいるから安心して」と答えた後、ぽつりと付け足した。
「安心ってのも、おかしな話だけどね」
「エクソスラムは若くして死去。自分が死ぬと判っていたからこそ、未来を管理者に託したのでしょう。彼の死後、ポトファトラムを扱える魔術師は未だ一人も現れておりません」と締めくくり、仁礼尼が立ち上がる。
「……茶を煎れましょう。お腹も減ってきたのでは、ありませんか?」
言われて初めて思い出したかのように可憐の腹が、グーと鳴る。
いや、腹の音が鳴ったのは可憐だけではなく、ジャッカーやアンナ、フォーリンのお腹までもが一斉に鳴った。
「あんなにハムハム食べたのに、また減ってきたのかい?そんなんだからブヨブヨしちゃうんだよ」
可憐が止める暇なくミルの嫌味が炸裂し、フォーリンは瞬く間に真っ赤に染まる。
「彼女はプニプニなんだと言っただろう。モミモミしたいぜ、その二つのおまんじゅう」
汚らわしいセクハラを呟くキースの首筋には、すかさずレンが手刀を振り下ろし、白目をむいて倒れたキースを部屋の隅に放置して、一行は額を突きつけあう。
「余計な真似をしてくれたもんだね、エクソスラムも」
むくれるミルに、珍しくドラストが同意する。
「あぁ、許しがたき魔法の悪用だ。おまけに異世界人まで己の野望に巻き込むとは、非道にも程がある」
「でも解決法が一つ見つかったんだから、それだけでもヨシとしなきゃ!」
ポジティブな前向き発言を繰り出したのは、ナナだ。
「後は、どうやってセキュリティーを突破して、その人に会いに行くかだけど……もっと有能な人を見つけてくれば、イケそうな気もしてきたわね」と、セーラ。
「有能な人って、例えば?」
ミラーの問いに「キースよりも有能な機械技師よ!」とセーラは鼻息荒く答えた。
だが国家規模のセキュリティーを突破するには、何年もの歳月を必要とするのではなかったか。
可憐は正直なところ、そこまで革命に付き合える自信がない。
ワ国の停戦にこぎつけた後はセルーン攻略を後世に任せて、隠居したい気満々だ。
セキュリティー突破なんて、技師の領分だ。スカウトの出る幕はない。
ワ国攻略後の〆アオリ文章は、これが妥当だろう。
『覇王戦争終結は、ここからだ!長年のご愛読ありがとうございました――』
「ちょっと待ってくれ」と、待ったをかけたのはクラウンだ。
無論、可憐の脳内〆アオリにケチをつけるつもりではない。
「セキュリティーを突破しても、その先にいるのは機械王だろう。管理者が同じ場所にいるとは、限らないんじゃないか……?」
「では、どこにいると予想しているんです?」
眉間に皺を寄せて、レンが聞き返す。
「それは判らん。だが、あんたらの話を聞く限りだと、既に機械王は管理の手を離れているように思う」
確かに自動修復まで出来るってんじゃ、管理の手は必要なさそうである。
「それも仁礼尼が知っているかもしれないね。戻ってきたら、聞いてみよう」
ミルが言った直後、襖がガラリと開き、何人もの女性が膳を運んでくる。
お茶を煎れると言っていたはずだが、夕餉を用意してくれたのか。
ググーとみっともなく腹の音を響かせながら、可憐は膳の前に座り込んだ。