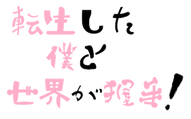世界は乙女ゲームで廻っている(かどうかは定かではない)
可憐共々、軍を脱走すると決めた当日――ユンはアナゼリア大尉のいる、最前線の駐屯地テントへ出向いた。
「緊急報告があるとの伝達でしたけれど。捕虜におかしな挙動でもありまして?」
雑談ぬきに本題を持ち出す大尉へ、無表情の鉄仮面でユンが頷く。
「その通りです、大尉。奴らは恐るべき計画を企てていました」
「恐るべき……?あの少数で、一体なにを」
怪訝に眉を顰める彼女に、ずずいっと接近し、ユンは声を潜めて囁いた。
「はい。失礼、お耳を拝借」
突然の急接近に、アナゼリアの胸は年甲斐もなくキュンと高鳴る。
三十八年生きてきて、ここまでの接近を異性に許したのは今日が初めてだ。
「……奴らの狙いは、あなたの純潔でした」
「えっ?」
すぐには言われた意味が判らず、ポカンとするアナゼリア。
そんな反応も置き去りに、ユンはキースの企てた口説き内容を、ほぼ棒読みで囁き続ける。
「一人だけ美麗な顔の男がいたでしょう。あれはクルズから放たれし刺客で、あなたを狙っていたのです、大尉。あなたを虜にして、クルズの忠実なスパイに仕立て上げるつもりだったのです」
「えっ……えぇぇ!?し、しかし彼らは私を初めて知ったかのような反応を」
「演技です」
演技もクソもない棒読みのユンに言われても、アナゼリアは、そこに突っ込む余裕がない。
彼女の脳内は、状況の推測でフル回転していた。
クルズは、ついこの間まで同志イリュータが引っ掻き回していた相手だ。
たとえ正気に返った皇帝の元で内政を立て直したとしても、セルーンへの反撃まで、こんな短期間で企てられるとは到底思えない。
それに、彼らはイルミ経由の海路でセルーンに侵入してきている。
クルズの姦計ならば、クルズから直接セルーンへ侵入しそうなものではないか。
だが、それもクルズの策の一つだとしたら?
イルミに罪をなすりつけるつもりで、イルミ経由の海路にしたとも考えられる。
考え込む大尉の耳元で、ユンがぼそっと囁いた。
「しかし、ご安心を。大尉の操は自分が必ずお守り致します」
「えっ!?」となって顔をあげたアナゼリアの前には、にっこりと微笑むユンの顔が。
あのユンが、家族や上司が相手でも仏頂面ないし能面を崩さない、ユンが!
乙女向け娯楽本に出てくるイケメンの如き柔らかな笑みを、自分に向けているッ!!
――と、そこまで考えた時点で、アナゼリアの思考はボンッと爆発急停止した。
真っ赤になって硬直する彼女に、ユンのイケメンボイスが耳元をくすぐってくる。
「あなたには断じて手を触れさせませんので、ご安心を。あなたは自分の妻となられる、大切なお方なのですから」
「へうっ」
しゃっくりのような変な声を出し、アナゼリアは自分よりも背の高いユンを見上げた。
これまで全く棒読みだったのに、今のユンときたら、どうだ。
優しい笑顔を浮かべて、慈愛の視線を注ぎ、その姿はまるで天使か騎士のよう。
いや、アナゼリアを守る、アナゼリアだけの忠実な愛の騎士だ。
「わ、私をアナタのお嫁さんに?それは、本気でおっしゃっておりますの?」
顔が熱い。ユンに至近距離で見つめられているからか。
いつもなら、ここで無表情に頷くだけのユンが、今は笑顔で「本気ですとも」と頷く。
笑顔というだけで、何故こうも眩しく感じるのか。
それは、アナゼリアも彼を好きだからだ。
彼を好きなのは彼の産まれが良い家柄だから、ではない。
彼自身に好意を持っている。
彼が入隊してきた時から、ずっと――
アナゼリアの目が半ば白目をむいているのを確認し、ユンは持参の酒をグラスに注ぐ。
純情な大尉を、これ以上欺くのは気が引けたが、キースの立てた作戦上、致し方ない。
美人だけど恋人歴全くナシな件や、本当は乙女向け娯楽本を愛読している件など、ユンは下位兵士の知らない大尉のプライベートを幾つか知っている。
ユンの父親経由の情報で。
大尉がユンの奥方になりたがっているとユンに教えたのも、ユンの父だ。
聞かされた当時は蛇足な情報だと切り捨てたが、こんな場面で役に立つとは侮れない。
こうしたアナゼリアの個人情報はキースやセーラなど、自分の部下にも伝えてある。
秘匿という考えは、当初のユンにはなかったのだ。
父が話してきたのだから、自分も他人に話してよいのだとばかり思っていた。
あとでキースにプライバシーの侵害だと突っ込まれて、悪い事をしたと反省した。
ユンの嫁になりたいと願うアナゼリアに対し、父は呆れていた。
歳の差も家柄も弁えず――と、頭から彼女を見下しているようでもあった。
実際に部下として働いてみれば、大尉は父が言うほど下賤な輩でもなく、ちょっと強気で強引な処はあるものの、しかし至って有能な上司であった。
まぁ、だからといって結婚したいかというと、それはそれ、これはこれだ。
再び柔和な笑顔を表面に貼りつかせ、ユンはアナゼリアを見つめる。
「これより、私は、あなたの護衛につきましょう」
「え、えぇ……願ってもないことですワ」
与えた任務の放棄は許せないといった思考は勿論大尉の脳内に浮かんだのだが、至近距離でのイケメン笑顔に負けて常識は右から左へすり抜けた。
「では、私とあなたの未来を祝福して……乾杯」
ユンは酒がなみなみ注がれたグラスをアナゼリアの手に渡し、自らもグラスを高く掲げる。
何故ここで乾杯せねばならないのかは、ユンにも疑問である。
だがキース発案のシナリオでは、ここで乾杯なのである。
アナゼリアと同じぐらい恋人いない歴の長いキースの案を採用するのには、抵抗があった。
しかし『お前も恋愛に関しちゃ似たようなものだろう』と突っ込まれては、ぐうの音も出ない。
近年、セツナ女医と男女のおつきあいを始めたが、遅々として関係が進まない。
せいぜいキスした程度だ。もっと親密になりたいのだが、距離を縮める方法が判らない。
――思考が脱線した。
今は、大尉に眠り薬入りの酒を飲ませて眠らせるのが先だ。
「か、乾杯……ッ」
ぼうっと頬を赤らめて、アナゼリアもグラスを掲げる。
捕虜が陰謀を企てているとなったら、乾杯している場合ではないと思うのだが、それすら今の大尉には思いつかなくなっているらしい。
大尉は、ぐいっと飲み干した直後、バターン!と勢いよく床に倒れる。
慌てて抱えあげてみると、涎をたらして爆睡していた。
ユンが知る限り最短最速、超即効性の眠り薬だ。
こんな劇薬を調合できるキースも、つくづく味方で良かったと言わざるを得ない。
この睡眠薬を、例えば井戸にでも放り込まれたら国一つが一瞬で全滅しかねない。
足音を忍ばせてテントを出ながら、キースには調合を今後一切禁止させようとユンは考えた。
ユンがアナゼリア大尉を、だまくらかしている頃。
密かにセルーン海軍第七艦隊駐屯本部へ戻ってきた可憐一行は、倉庫に身を隠す。
キース曰く、この倉庫は現在全く使われていないとのことだ。
元々セルーンの駐屯地は、どこもテントで機能しており、倉庫を建てる意味がない。
なのに決算の不備をごまかすべく王様ヒゲ少尉が無理やり作ったのが、この倉庫だった。
「どこの国も、偉い人は悪い奴が多いんだねぇ……」
判ったようなそうでもないような呟きを漏らす可憐に、ドラストが憤慨する。
「違うぞ、カレン。クルズやセルーンが不誠実なだけだ。今の我がイルミには悪い奴など一人もいないからな」
「へー、今のってことは昔は、いたの?偉くて悪い人」
ナナによる直球な重箱の隅突きが飛ぶ中、可憐は倉庫内を見渡した。
見事に物が何もない。がらんどうの箱、そう称しても差し支えあるまい。
決算の帳尻を合わせる為に作られただけあって、本当に使用されていないようだ。
「ここは広い上、音も防音されている。任務をサボるのに快適でな」
ニヤリと不敵に笑うキースを見て、なるほどと可憐は確信を深める。
自分の所属する艦隊長が駐在する本拠地でサボるたぁ、筋金入りのポンコツだ。
同時に、こんなサボリ魔を仲間に入れて大丈夫なのかと不安にもなった。
なったがしかし、仕事を嫌がる点においては可憐だって負けちゃいない。
高校を出てから一度も就職したことのない可憐が、とやかく言えた義理はないのだった。
まぁ、何とかなるだろう。ここでも可憐は気楽に考え直す。
なんせ元ニートの自分が重宝されているぐらいなのだ、この一行は。
一人二人サボリ魔が増えたところで、ミルやエリーヌなどのしっかり者が何とかしてくれる。
その、しっかり者達だが、倉庫に潜んでからは、めっきり大人しい。
てっきり、ここでもガヤガヤ雑談するかと思っていたジャッカーまでもが静かだ。
と思っていたら、アンナが口を開いた。
「あなた方の立てた作戦に、不満はありませんが……ここへ来るまでに下級兵士に一人も遭遇しなかったのが、気になります」
「あぁ、それはだな」と、キースが説明するところによると。
現在、第七艦隊はヌマポッカ海峡の防衛を命じられている。
ここはセルーンとイルミ双方の海軍がぶつかりあう、海の戦場最前線であった。
一から十まで、全ての小隊を出撃させねばならぬほどの激戦区だ。
第九小隊は人質の監視を任された為、この任務からは外された。
一つ小隊が減って激戦のハードルがあがり、今は不眠不休で他小隊が出撃している。
人が少ないのは当然だ。ほとんどの兵が海に出ているのだから。
「ここに救護施設はないから、軍医もいない。そもそも軍医は普段、首都待機だしな。特命でもない限り、こっちには来ん。あとは飯炊き奴隷が少々だが、原則俺たちのいる区域への立ち入りを禁じられている。船の整備は兵士が自らやる義務だ。ま、実際には俺達第九小隊が任されているようなもんだったが」
「なるほど……セルーン軍って上はユルユル、下はガバガバ……」
「卑猥な言い方をするんじゃない」とキースに突っ込まれ、逆に可憐は「えっ?」となる。
何も、シモネタギャグを飛ばすつもりで言ったわけではない。
管理体制が、いい加減だと言おうとしただけなのに。
抗議しようと思ったが、キースが手元の黒い機械を弄り始めたので、やめておいた。
通信機にもなると聞かされていたから、きっとどこかへ連絡を取るのだろう。
キースが黙ってしまうと、いよいよもって倉庫内は静まり返る。
沈黙に耐え切れず、ややあって可憐はポツリと呟いた。
「……ユン、まだかなぁ」
ミラーが「すぐ戻ってきますよ」と相槌をうち、ジャッカーも雑談に加わってくる。
防音だと知って、多少は雑談する意欲も戻ってきたか。
「クラマラスとは、どこで合流したらえぇんやろ」
「海にさえでれば呼べると思うよ」と答えたのは可憐ではなく、ミル。
「なんだ、クラマラスとは」と横入りしてきたキースにも、ミルが答えた。
「ボク達の仲間さ。モンスターだけど、友好的な奴らだよ」
「ほぅ、モンスターまで手なづけているとは、クルズの召喚師は侮れんな」
ミルの手柄だと勘違いしているので、ここぞとばかりに可憐は言ってやった。
「あいつらをスカウトしたのは俺だからね」
嘘ではない。
彼女達は可憐の口車に乗って仲間になった。
これだけは可憐が誇れる、唯一のスカウト功績だ。
クラウンが仲間になったのは可憐がいてこそだが、可憐がスカウトしたわけではない。
クラウンを探そうと最初に考えたのは、エリーヌである。
ジャッカーが仲間になったのも、ほとんど成り行きだ。その場のノリで仲間になった。
彼女はクラウンが呪われていなかったら、話しかけてもこなかっただろう。
アンナとミラーは船を調達する際、どさくさに紛れて仲間に引き込んだ。
これもスカウトというより、その場のノリに近い。
「そして、今度は俺達がお前にスカウトされたというわけだ」とキースに言われて、きょとんとする可憐は鼻先に指を突きつけられた。
「なんだ、自覚がない顔をしやがって。お前は俺に言っただろう、一番最初に。お前と旅をすれば、世界中でモテモテになれると。なるほど、確かに世界を平和に導くとなればモテハーも現実味を帯びてくる。共に手を取りモテモテハーレム王国を築こうじゃないか、なぁカレン?」
動機は限りなく不純だが、一応可憐のスカウトで加入したと考えて、いいんだろうか。
第九小隊の、少なくともキース一名に限っては。
「あたしの目的はモテハーじゃないけど」と、ナナが断ってくる。
「世界平和はセルーンの軍人だって、願ってやまない未来だもの。その、お手伝いが出来るんだったら、なんだって協力するわ!」
いい感じに雰囲気が温まってきたところで、ようやくユンが倉庫に駆け込んできた。
「ユン、ナイスタイミングだ。俺達の友情伝説が、ここから始まる瞬間だぞ」
わけのわからないキースの戯言をまるっと聞き流し、逆に尋ね返してくる。
「セツナと連絡は取れたのか?」
「あぁ、ラッキーだったな。奴は直接、船に向かうそうだ。俺達も急ごう」
セツナとは誰なのか。
ユンに尋ねる間もなく急かされて倉庫を出た可憐一行は、船の前で本人と合流する。
セツナは海軍に所属する医者だった。
本来首都にいるはずの軍医が何故ここに急行できたのかというと、彼女は偶然この付近の村に派遣されていた。
医者のいない区域に首都の医者が派遣されるのは、王の定めた法に基づく義務である。
第九小隊とは面識があり、以前、彼らの受けた特務にも同行したらしい。
その縁で、ユンに呼ばれたから来たのだと彼女は可憐達に告げた。
ミソッカスが一体なんの特務を、と首を捻る可憐を余所に、アンナは周囲を見渡した。
激戦になるのではと怯えていたのが馬鹿らしくなるほど、ドッグは閑散としていた。
閑散どころか人っ子一人いない。いるのは自分達だけだ。
本当に雑魚兵は全員、戦場へ出払っているようだ。
セツナ医師曰くヌマポッカ海峡の戦況は芳しくなく、首都でも問題になっている。
近々第七艦隊にかわって第六艦隊を派遣するのでは、といった噂も立っていた。
危なかった。キースの予想していた通りだ。
もし交代していたら、可憐達はセルーンを脱出できなくなっていたかもしれない。
「さぁ、出発進行。ちょいと揺れるかもしんねーが、そこは根性で踏ん張れよ?」
操縦席に座ったカネジョーに言われて、そういや酔い止めの薬を塗るのを忘れた――!
と可憐が気づく頃には船が急発進し、ぐいっと引っ張られる重力を身に受けながら。
あとは一気に迫りあがってくる吐き気との戦いで、可憐の思考はいっぱいになった。