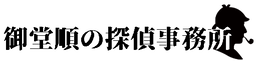探偵事務所のハロウィン ~2020 Halloween~
吹きっさらすのは、何も北風ばかりではない。懐の中身も最近がくんと減ったのではないかと、光一は内心溜息をもらす。
このコロナ渦において、御堂順の経営する探偵事務所も例外ではなく。
客足は確実に、前よりも減った。
心なしか近所の商店街も、人影は減ったのではないか。
経済回復効果を狙ってのGoToナントカも抜け道を突かれて大混乱だし、何とかならないもんかねぇと首を振り振り事務所へ戻ってみれば、学校帰りのガールフレンドが遊びに来ていたところであった。
「今月はハッピーハロウィン!だってのに、どこもシケてんのよねェ~」
ぐちぐち文句の多い成実に、所長は「そんなの知るかよ」と素っ気ない。
「んなことより、ガッコでも三密作るなって言われてんだろ?オラ、帰れ帰れ」
身内とはいえ、せっかく遊びに来てくれたお客様に対して超塩反応だ。
所長の態度がそんなんだから、コロナがなかったとしても客足が寄りつかないんだよと内心愚痴りながら、光一は笑顔で成実に話しかけた。
「成実はハロウィンを祝いたいんだな?その気持ち、判る判る」
「でっしょ~。さすが光一、判ってるじゃない」と、成実は嬉しそう。
「こうなったら、事務所だけでもハロウィンしよっ!」と盛り上がる二人に水を差してきたのも所長で。
「するわけねーだろ。仕事が入らんようなら解散だ、解散」
ちらっと壁にかかった時計を見やり、光一は甘ったれた声で応戦した。
「営業時間終了まで、まだたっぷり時間があるんですよ。暇つぶしにやりませんかぁ?ハロウィン」
が、言っているのが可愛げのない二十歳越えた助手では、御堂の心も動くわけがない。
「うるせぇ、そんなにハロウィンがやりてぇんなら、お前ら二人だけでやってこい」と来たもんだ。
「も~、なんだってそんなに何もやる気ないのよ。そんなやる気のなさじゃ、そのうち、事務所も潰れちゃうんじゃないの?」
成実に理不尽な内容で怒られ、「ハロウィンをやる気になったら、客足が戻るってーのかよ」と所長も屁理屈で反論する。
次第に険悪ムードが増していく中、チャイムが鳴って、光一は、これ幸いとばかりに飛びついた。
「はいは~い!どちら様ですかぁ」
するとインターホンの向こう側からは『Trick or Treat?』と返ってきて、オヤ、近所の子供にしては声が妙に渋いなぁと光一は疑問に思いつつも、用意していたビニール袋から幾つか駄菓子を取り出した。
昨日のうち、近所のスーパーで買っておいたお菓子だ。
「もちろんトリートだ、うん、トリート以外ありえないよ!ハッピーハロウィーン♪」
勢いよく扉を開けてみれば、「おっと」と呟き一歩退いた相手と鉢合わせる。
「あれっ、竜二?」
「竜二だとォ?」「え、なになに、トバッち遊びに来たの?」
勢いで御堂と成実の二人も玄関先へ飛び出してきて、来訪者の竜二がぺこりと頭を下げた。
「お久しぶりです、皆さん」
手には大きな鞄を下げている。営業帰りだろうか。
「わ~トバッちが、こんなタイミングで来てくれるとか思ってもみなかった!」
素直に喜ぶ成実と裏腹に、所長は素直じゃない一言を漏らす。
「なんでぇ、ヤクザはハロウィン参加禁止じゃねぇのかよ」
「配るのは禁止ですが、参加するなとは言われちゃいねェんで」と竜二もやり返し、ただし菓子を本当にもらえるとは思ってもいなかったと付け足した。
「でしょー。うちは大人から子供まで、ハロウィンを祝う人には全員お菓子を配る予定だから」と勝手な予定を宣う光一に、すかさず御堂の突っ込みが飛ぶ。
「全部お前が出すんだろうな?俺ァ、一銭たりとも参加してやんねぇからな」
「ハイハイ、もちろんですとも、判ってますとも。さぁ、参加しない人は、あっち行って、邪魔邪魔」
野良犬を追い払う仕草で所長を隅っこに追いやると、光一は成実と竜二へ微笑みかける。
「これから先、営業終了時間までに何人来るか、楽しみだね」
だが、「多分、もう誰も来ないんじゃないかしら」などと盛り下がる発言をかましてきたのは意外にも成実で、ちらっと壁の時計へ視線をやる。
「大体営業終了って、あと二時間もないじゃない。だったら、このメンバーで祝ったほうがマシよね。ハロウィンは一日しかないお祭りなんだし」
しかし、今からやると言われても。
仮装するには準備が足りないし、お菓子を配らないなら、することもない。
首を傾げる光一の口に無理矢理クッキーを押し込んで、年下のガールフレンドは微笑んだ。
「三人でお菓子交換会をしようっての。つってもトバッちは持ってきてないだろうから、光一、あんたのお菓子で交換会よ」
当然のように成実も手ぶらで来ているから、実質光一の用意したお菓子での交換会だ。
「なんだそりゃ、何が面白いんでぇ」と外野から飛んできた野次は華麗にスルーし、竜二が手を挙げる。
「お菓子交換会もいいんですが、悪戯をメインにするってなぁ、どうでしょう?」
「悪戯を?」
「なるほどー……」としばらく黙った成実、何を思ったのか突然はさみと紙を手に取って、ちょきちょきと切り始める。
「おい、そろそろ店じまいだってのに散らかすんじゃねーよ」と怒る所長などそっちのけで、今し方作った出来合いのくじを二人に差し出した。
「くじびきでランダム悪戯大会開始!アタリを引いた人にだけ、悪戯の特権が与えられま~す」
「いいね、いいね、あと二時間の暇つぶしにもってこいだ。おりゃっ!」
最早営業時間であることすら忘れているとしか思えない態度で、光一もノッてくる。
だが、どのみち、ここ数ヶ月は依頼がぱったり途絶えている。探偵事務所も、そろそろ閉め時か。
いやいや、しかし光一と二人で暮らすにあたり、年金も出ない御堂は事務所を続けるしかない。
いざとなったら光一を、どこかのアルバイトとして働かせるしかないだろう。
しかし、それもコロナ渦、雇ってくれる店があるかどうか。
憂さ晴らしと暇つぶしを兼ねて、ハロウィンしようと言い出す光一の気持ちも判らなくはない。
やけくそになってきた御堂の前に、ぬっとクジが突き出される。
「……俺は参加しねぇっつったぞ?」
じろっと竜二を睨みつけると、「こんな時こそ、気持ちだけでも明るくなりやせんか」と竜二が苦笑した。
続けて「心配だったんです」と切り出されて何がと御堂が促してみると、竜二は語り出す。
緊急事態宣言が解除されても、人々はコロナを恐れて外で騒ごうとしなくなった。
池袋も渋谷も、今年のハロウィンは中止の方向だ。
このまま辛気臭く部屋にこもっていたら、日本全体がおかしくなりそうだ。
不意に、御堂の探偵事務所を思い出した。
この不景気、ヤクザだって収支にキリキリさせられている。
あんなチッポケな探偵事務所では、とっくに潰れているかもしれない。
御堂と光一は竜二にとって恩人だ。何かできることが残っていればいいのだが――
そう思ったら居ても立っても居られなくなり、ここへ駆けつけた次第だという。
「竜二ってば……なんてイイコなの!ヤクザなのに」
何故か年下の光一には子ども扱いで頭をナデナデされ、肝心の御堂には口を尖らされる。
「この程度の不景気で潰れるほどにゃあ不景気慣れしてなくねぇんだよ、こちとら」
だが、と少しばかりテレくさそうに小さく呟いたのを、竜二はしっかり耳にした。
「……心配してくれて、ありがとよ」
「はい、じゃあゴキブリ並みにしぶとい所長、クジをひいてちょーだい」
成実にクジを急かされて、その手を鬱陶しそうに払う頃には所長の調子も戻っている。
「うるせぇ、アタリは竜二で決まりだろうが。客を喜ばせてナンボの探偵事務所ってもんだ」
クジを引かずして、当たりにされた竜二もポカンと驚きだ。
その竜二に、光一が満面の笑みで尋ねる。
「竜二は、どんな悪戯してみたい?所長の髭を全部ゾリンゾリンに剃っちゃうなんてのは、どぉ?」
「光一ィ!」と苛立って騒ぐ御堂をも一瞥し、竜二も笑みを浮かべて答えた。
「それじゃ、台所を貸してもらえますか?一つ、手作りの菓子でビックリさせてやりやしょう」
「えーっ!?竜二、お菓子作れるの!」
作る前から驚く光一の横で、成実も尋ねる。
「作るっても、材料は?」
「そいつは抜かりなく、持ってきてまさぁ」と、竜二が見せてきたのは手持ちの鞄。
お菓子を配るでもなく仕事でもないのに大きな鞄を持っていると思ったら、最初から、そのつもりで遊びに来たのだと言う。
それにも驚きだ。配るのを禁止されたから、作ることにしたのか。
「やっぱトリートは良い文明……そう思うよね、所長も」
うきうき浮かれる光一を横目に、いそいそと紙の使い捨て皿を並べ始めたのは、成実ではなく御堂所長その人だ。
「おう、驚いてんじゃねぇよ。ハロウィンに参加しろっつったのは、おめーらだろ?なら竜二の手作りおやつ大会、とくと三人で堪能しようじゃねェか」
大口あけて眺める若者二人を振り返り、御堂は久方見せなかった、とっておきの笑顔を浮かべたのであった。
おしまい