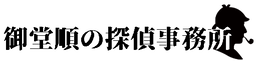籠の中で
俺が山口組から大西組へ移籍したのは、五十鈴と結婚してから二年と経たない、寒い雪の日だった。ヘッドハンティングなんて言えば格好いいが、実際は、そんな格好いいものじゃない。
うちの事務所まで乗り込んできた大西敬司と、殴る蹴るのタイマンを繰り広げたのだ。
大西敬司は五十鈴の元旦那だった。
かつて彼女と大西が夫婦として仲良く――というには多少冷え切った関係だったが――やっていた頃、夫婦生活を打ち切るべく現われたのが、俺という存在だった。
俺だって、何も好きで二人の夫婦生活をぶち壊したかった訳じゃない。
その頃の俺は荒んだ生活をしていた。
高校卒業と同時に逃げるように家を飛び出した俺は、とある工場のコンベア工員として働き始めた。
だが働き始めてすぐ、工場の先輩からは何かと虐められるようになっていった。
目つきが悪いだの、態度が悪いだの。
あまりにムカつくから、ある日、ちょっと反抗してやった。
要は、殴ったんだ。先輩の一人を。
その日を最後に嫌な噂だけが一人歩きして、気がついたら工場をクビにされていた。
話し合いも何もなく、一方的に悪者扱いさ。ツイてねぇ。
それからの俺は、語るまでもないだろう。
ゴロツキ相手に暴力を振るい、あてのない日々を送っていた。
そこへ現われたのが、山口五十鈴だった。
五十鈴は誰が見ても、いい女だった。
胸がでっかくて、腰はキュッと引き締まっているくせに、尻が撫で回したくなるほど大きいんだ。
年の頃は二十から三十代。
まぁ、女は化粧で化けるからな。見た目なんて、アテにならない。
五十鈴ってやつは、とにかく賢い女でね。
話のツボッて言うのかな、人を楽しく会話させるツボを掴んでいた。
とにかく、安っぽいバーで出会って以降、俺達は急速に仲良くなっていった。
彼女がヤクザの親分の一人娘だと知ったのは、随分あとになってからだ。
そう、婚約しようって話が出た頃だったと思う。
親に紹介するからと渋る俺の腕を引っ張って、彼女の実家へ連れてこられた時にゃあ、さすがに怖くなったね。
だってさ。床の間に飾ってあるんだぜ?日本刀が。
『任侠』なんて書かれた掛け軸は下がっているし、いくら無知な俺でも彼女の親父がヤクザだと、すぐに判ったよ。
内心青くなる俺を前に、彼女の親父は言ったんだ。
「君を一目見て気に入った。五十鈴が君を気に入るのも、よく判る」って。
何をどう気に入られたんだか判らないうちに、俺は五十鈴との結婚届に判を押していた。
で、彼女とめでたくゴールインしたってわけだ。
その日、俺と彼女は初めて床を一緒にした。
――だが甘い新婚生活だったのも、そこまでで。
結婚の翌日から、彼女はガラリと変わっちまった。
俺を一人前の極道に仕立て上げるべく、五十鈴は鬼嫁に変化してしまったのだ。
来る日も来る日も体力作りに真剣の素振りをやらされて、ほとんど外には出してもらえない日々が続いた。
毎日が鳥かごの中みたいで、俺は、いつしか外に出たいという願望を持つようになっていた。
大西敬司率いる大西組が攻めてくるようになったのは、俺が五十鈴と結婚して一周年を迎えた頃だ。
その頃には俺も高校の時とは比べものにならないほど、強くなっていた。
肉体の変化だけじゃない。
がむしゃらな喧嘩とは違う、戦いの間合いが読めるようになったんだ。
五十鈴に無理矢理習わされた、ボクシングの成果だろう。
大西組は徐々に山口組のテリトリーを侵食してきていて、前々から問題には、なっていた。
問題が一気に爆発したのは、テリトリーの境界線を巡って、うちの若い組員と向こうの組員が衝突した件でだ。
向こうが先にふっかけてきたとは若い組員の話だが、俺は今でも仕掛けたのは山口組が先だと思っている。
ま、どちらが先にせよ、抗争は些細なきっかけで始まってしまった。
そして数の暴力とでもいうべきか――
山口組は大西組の大軍を前に劣勢となり、ついには事務所にまで乗り込まれてしまったというわけだ。
五十鈴を守るべく俺も奮闘したのだが、大西の強さは圧倒的で、彼女の目の前でボッコボコに叩きのめされた。
でも、彼は五十鈴や山口の親分に対して何もしなかった。
そう、何も暴力をふるったりしなかったんだ。
俺が守る意味など、最初から全くなかった。
彼は最初から、五十鈴に危害を加えるつもりで乗り込んできたんじゃない。
それを知ったのは、俺が彼に誘われて大西組へ移った後だった。
「どうした?竜二。ボーッと考えこんじまってよ」
ふと、肩を掴まれ我に返る。
振り返ると、大西さんの笑顔があった。
いつの間にか、事業終わりの時間が過ぎていたようだ。
部屋が、すっかり暗くなっている。
「いつも悪ィな、独りぼっちにしちまって」
思いがけぬ謝罪に、俺は慌てて首を振った。
「いえ、大西さんには気を遣っていただいて、感謝しておりやす」
大西組に移ってきて、しばらくは下っ端組員として扱われるかと思いきや、俺は大西敬司の秘書として社長室の隣に入れられた。
秘書といっても、やることは何一つない。
毎日、部屋の中で大西さんの帰りを待つのが、俺の仕事だ。
籠の中の生活だ。山口組にいた頃と、何も変わらない。
変わったのは、相手が五十鈴じゃなくて大西という男になった点だけ。
大西は何故、俺をヘッドハンティングしたんだろう。
彼の帰りを待つ間、日増しに俺の中で疑問は大きく育っていった。
山口組を抜ける時だって、一悶着あったのだ。
五十鈴は勿論、親分だって俺が抜ける件については、首を縦に降ろうとしなかった。
ま、当たり前だがな。
次期組長になろうって男に抜けられたんじゃ、極道としての示しがつかない。
結局のところ、俺は五十鈴の制裁を一方的に受けることで、なんとか抜ける許しを得たのだ。
三日三晩、傷の痛みでうなされたのは、言うまでもない。
やる時は徹底的にやる女だというのは判っていたが……本当に、あの時の彼女は容赦なかった。
それ以来、彼女とは一度も会っていないが、きっと恨んでいる事だろう。大西さんの事を。
組のテリトリーを半分以上奪われたばかりか、俺という旦那まで奪われちまったんだからな。
え?山口組を抜けた理由?
あのまま山口組にいたんじゃ、そのうち、きっと大西組に潰されると見切りをつけたからさ。
沈みゆく泥舟にしがみつくよりは、逃げ出した方がいいに決まっているだろ?
ともかく俺は名実と共に晴れて大西組の仲間となり、鳥かご生活を再開したってわけだ。
俺が仲間になることで、面白くない気分を味わった奴もいたようだが、数日後には俺は皆に受け入れられていた。
――大西さんの『愛人』という扱いで。
部屋からは一向に外へ出してもらえないものの、大西さんは俺に優しくしてくれた。
その日あったことや、見聞きしてきた面白いニュースなどを俺に聞かせてくれ、夜は同じ部屋で眠る。
いや、誤解して貰っては困るが、同じベッドで寝ているんじゃねぇ。
ベッドは別々だ。別々だが、部屋は同じだ。
なのに、俺はいつの間にか大西さんの愛人扱いを受けていた。
同じ部屋で寝ている、というだけで。
だが、どうせ何を言っても、俺の意見など聞いてくれる奴はいないだろう。
どうでもいいやと俺も捨て鉢な心境になり、噂をしたい奴は、すればいいと放っておくことにした。
だから、あの晩。
ヤケクソになっていた俺が、夜にやってきた相手を確認もせず部屋に招き入れたとしても、誰が俺を責められようか。
悪いのは、いつも勝手に俺のイメージを決めつけてしまう皆なんだ。
その日、大西さんは、いつになく帰りが遅かった。
普段なら遅くても十時までには帰ってくるのに、その日に限って、十一時を回っても帰ってくる気配がない。
今夜は来ないのか――待つのを諦めて寝ようかという時、扉がノックされたので俺は飛び起きた。
別に心待ちにしていたつもりはないんだが、やっぱり心の何処かでは嬉しかったんだろうな。
廊下は真っ暗だった。それでも俺は何の疑いも持たずに、相手を真っ暗な部屋へ招き入れた。
「随分と遅かったですね」なんて、嬉々として言いながら。
――異変に気づいたのは、招き入れた相手に背を向けた次の瞬間、抱きつかれた時だ。
「おッ、大西さん!?」
振りほどこうにも、相手のほうが上背があって、なかなか振りほどけない。
耳元に生暖かい息を吹きかけられた。
「やっぱ大西と、乳繰りあってんのかヨ?」
聞き覚えのある、低いダミ声。こいつは……茨城賢治?
部屋に囲われる前、一度だけツラ合わせをしている。
大西さんを呼び捨てる茨城に、多少、苛つかされたのを覚えている。
大西組で唯一、大西さんに敬意を払っていない組員など、こいつぐらいなもんだろう。
だが、そいつに何故、俺が抱きつかれなきゃならないのか。
「エッ、毎日、乳繰りあってんのかって聞いてるんだヨッ!」
腕が自由になったと思ったのも一瞬で、両方の乳首を服の上からギュゥッと摘まれた俺は総毛立つ。
こいつ、何しやがるんだ?男の乳首を摘んで何が楽しいっていうんだ。
「放せよ、この……ッ!」
自由になった腕で肘を繰り出すが、この体勢じゃ勢いが出ない。
肘鉄は虚しく、相手に受け止められた。
「竜二ちゃんは毎日、あのベッドで大西とヤりあってるってェわけだ……」
足が、ふわりと宙に浮いた。
抱きかかえられた格好で、ずるずるとベッドに引っ張られているのだと判り、俺は必死で抵抗する。
しかし巨象に吊された小猿の如く、悲しいほどの体格差が俺の逃亡計画を無惨にも打ち砕いた。
畜生、馬鹿みてぇにデカイ図体しやがって。
上背だけなら大西さんとタメを張るレベルだ。
それに、誰が誰とやりあっているって?
俺と大西さんの名誉の為に言っておくなら、ベッドで乳繰りあったことなんざ誓って一度もない。
「ぐっ……」
乱暴にベッドへ叩きつけられる。
同時に茨城の巨体がのし掛かってきて、身動きが取れなくなった。
「ど……けッ」
肺が苦しい。茨城が上に乗っかっているせいだ。畜生。
ビッと布の破ける音がして、俺のシャツが景気よく破られる。なんて馬鹿力だ。
よくドラマなんかで、抵抗する女の服を破るシーンを見かけたことがあるだろう。
でも実際、服を破るってのは生半可な腕力で出来る所業じゃない。
相当力を入れても、普通の奴なら雑巾一枚だって破れないはずだ。
だが、いとも簡単に茨城は引き裂いてみせると、露わになった俺の胸元をベロベロと舐めてくる。
冗談じゃない。気持ち悪い。
引きつる俺の顔を見て、茨城が汚い顔を、更に汚くニヤァッと歪めて笑った。
「どうしたィ、大西さんの愛撫じゃねぇと感じねぇってか?」
「だ、誰が、んな事を言ったってんだ……!さっさと、どきやがれッ」
どけと喚いたところで奴がどくわけないと判っていても、俺は言わずにおれず騒いだのだが、やはりというか当然というか茨城がどいてくれる気配はなく、ズボンのチャックまで無理矢理引き下ろされた。
ぞぉっと俺の背筋に悪寒が走る。
まさか、まさかとは思うが、こいつ――
俺の予想を裏切らず、茨城の手がズボンの中へ入り込む。
思い切り金玉を掴まれた。
「んぁッ!」
掴まれただけじゃない。
モミモミと揉まれて、俺の口からは恥ずかしい悲鳴が飛び出す。
嫌だ、男に掘られるなんて絶対に嫌だ。
俺は藻掻くが、マウントポジションを取られた格好から奴の巨体をはね除けるなど、どだい無理な話で。
巨象に踏みつぶされた蟻の気分だ。
暴れれば暴れるほど、こっちの体力だけが失われてゆく。
奴の指が、後ろの穴に差し込まれる。
差し込まれたばかりか、グリグリとほじられて、俺は身をよじる。
「ククッ、気持ちいいのかィ竜二ちゃん」
「ち……がッ」
違う。気持ちいいどころの話じゃない。むしろ激痛だ。痛い。
痛くて、だから逃れようと身をよじっているのだが、茨城は俺を逃さず、更に指を奥へ突っ込んでくる。
畜生。なんで、こんな奴に無理矢理カンチョーを強いられなきゃいけないんだ。
「涙が出てきたゼ?オー、ヨチヨチ、初めてなんでちゅねー竜二ちゃん」
痛みのあまり、どうやら俺は涙ぐんでしまったらしい。情けないにも程がある。
しかし涙を拭おうにも、絶えず奴が肛門を抉ってくるもんだから、こっちは身動き一つ取れやしねぇ。
肛門を弄られると同時に、金玉も揉まれている。前と後ろのダブル攻撃だ。
絶体絶命ってのは、こういう状況を言うのかもしれない。
生まれて初めての経験に加え、逃げ場を失ったショックも手伝って、俺は半ば意識朦朧としかけていたのだが――
救いの神は、やや遅れた時間に登場した。
「茨城ィ、テメェ!!!」
普段の陽気な大西さんからは想像もつかぬ怒号が聞こえたかと思うと、次の瞬間には視界が開ける。
何かが倒れ込む大きな音を耳にしながら、俺は大西さんに抱き起こされた。
「竜二ィ、どこも怪我してねーか?痛いところがあったら、ちゃんと言えよ!」
オロオロしながら俺の顔を覗き込んでくる。
これも、いつもの大西さんからは考えられない程の動揺っぷりだ。
彼の顔を眺めているうちに、俺の両目からは、また涙が出てきやがった。
なんだこれ、安心?安堵の涙ってやつか。
どっちにしろ、大西さんの前でも泣きべそかくなんて、情けねぇ。
ぼろぼろ泣き出した俺を抱きかかえ、大西さんが大声を張り上げた。
「おい茨城!テメェは破門だッ。二度と俺の前にツラァ、出すんじゃねーぞ!」
チッと小さく舌打ちして、茨城が立ち上がる。
大西さんの背中越しに見えた奴は、口の端から血を流していた。
きっと、大西さんに強か殴られたんだろう。いい気味だ。
「言われなくたッて、出てってやらァ、こんな組!!せいせいすンぜッ」
負け犬の遠吠えを残して、茨城が飛び出してゆく。
部屋には俺と大西さんの二人きりとなった。
「竜二ィ、竜二、痛いところはねぇか?変な真似されたんじゃないだろうな……すまねぇ、俺が遅くなっちまったばかりに!」
途端に大西さんは格好を崩し、またしてもオロオロしながら俺の体を調べ始める。
だが俺の胸元を見た瞬間、ハッとした表情を見せたかと思うと。
「茨城ィィィッ、あんのやろうッ!」
いきり立って部屋を出ていきかけたので、俺は咄嗟に彼の足を捕まえた。
「お、おう、どうした竜二?」
優しい目で見下ろされて、俺は「い……行かないで、下せェ」と言うのが、やっとだった。
ホントは遅くなった件についての愚痴を言いたかったし、茨城に対する文句の一つや二つも言いたかったんだ。
でも、なんかもう、どうでもよくなっちまった。
大西さんが帰ってきて、俺を助けてくれた。
それだけで、俺はなんか、すごく嬉しくなってしまったんだ。
あぁ、また涙が出てきやがった。しかも今度のは、なかなか止まらねぇ。
「りゅ、竜二……痛いなら、痛い場所を教えてくれ。きゅ、救急箱、持ってくるからよ」
立ち上がりかける大西さんのズボンの裾をギュッと握りしめ、俺は涙声で囁いた。
「いいから……今は、側にいて下せェ。それだけで、俺は、充分だから……」
うまく言葉にできないもどかしさ。
それでも大西さんには伝わったのか、俺の隣へ腰を降ろしてくれる。
「ん、あぁ、判った。……ごめんな、遅くなって」
何度目かの謝罪を耳にしながら、俺は、そっと大西さんの肩へ自分の体を預けた。
おしまい