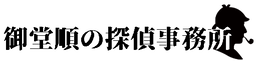竜二のお誕生日
子供の頃の記憶に、誕生会と呼べるものがない。父は飲んだくれのアルコール中毒、母は年中浮気相手の元に出歩いていたとあっては。
ドメスティックバイオレンスが発生しなかったのだけは、唯一の救いだ。
あとは何の想い出もない。故郷は捨てるに値する場所だった。
上京してからは安アパートを拠点にアルバイトを探す日々で、自分が幾つになったのかは覚えていても、誰かに誕生日を祝ってもらった事はない。
アパートに住んでいても、孤独なのは変わらなかった。
隣に誰が住んでいるのかもよく判らなかったし、交わす言葉は挨拶ぐらいだ。
ある日酔っぱらって喧嘩して、意識が遠くなって、気がついたら見知らぬ店に運び込まれていて、そこから五十鈴との交際が始まって、結婚、離婚、大西組への移籍。
……と、なんやかんやあって。
気がつきゃ三十になった、お祝いをされている。
人生、未来がどう転んでいくかなんて誰にも判らないものだ。
二十九歳の誕生日は、大西と二人で祝った。
いいって何度も言ったのに高そうなスーツと派手な腕時計をプレゼントされて、大層恐縮した。
今年の誕生日は、ひょんなことで知り合った御堂探偵の事務所が会場だ。
目の前にはイチゴの乗ったホワイトケーキが、でんと置かれている。
ご丁寧にも三十本の蝋燭が突き刺さって、マジパンで作られた看板には『お誕生日おめでとう、竜二ちゃん!』と書かれていた。
三十のオッサンが祝われるにしては、えらく幼稚なケーキだ。
「俺は太い蝋燭三本にしようって言ったんだけど、所長に押し切られちゃって。不格好でゴメンね、でも味は保証するから!」と笑いながら、光一が紅茶を人数分注ぐ。
「っていうか、大人の誕生日を祝うのにイチゴのホールはないよね」と、成実。
「もっとお洒落なケーキが良かったんじゃない?」と話を振られて、竜二は手を振った。
「いや、ありがてぇですよ。俺なんかの誕生日を、堅気の皆さんが祝ってくれるたぁ」
竜二はヤクザ、本来なら一般人と仲良くキャッキャできる立場にない。
だというのに探偵事務所の面々ときたら、全く気にせず竜二の携帯へ直接お誘いの電話をよこしてきた。
「シャレオツな飯なら、あとで大西の親分が奢ってくれんだろ。こっちは庶民派で対抗してみたんでェ」
御堂は胸を張り、横では光一が「ってのは建前で、本音は安売りしてたんだよね」と笑顔でネタ晴らしする。
近所の御用達ケーキ屋で三十パーセントオフセールがあったそうだ。そいつは、お買い得だ。
「まぁ、ホールケーキなんて誕生日でもない限り食べられないし」
「そうね、しかも生クリームのイチゴケーキ!下手したら小学生以来じゃない?」
成実は光一の隣に腰かけて、御堂が蝋燭に火をつける。
「ハッピバースデー、ツーユー♪」
徐に歌い出した光一に併せて、三人は手拍子を取りながら合唱してくれた。
フィクションでは多々見たことのある光景だが、実際に見たのは初めてだ。
友達の誕生会にだって招かれた記憶のない竜二は、ポカーンと呆けて誕生日の歌を聴いた。
いや、そもそも友達なんて幼い頃は一人もいなかったじゃないか。
友人と呼べる間柄が出来たの自体、御堂たちと知り合って以降だ。
ふっと温かいものが竜二の心を包み込む。
あぁ。これを幼少の頃に体験していたら、もっと違った人生が開けていたかもしれない。
だが、今の人生をやり直したいとも思わない。
大西と知り合った時点で、竜二の人生は分岐点を迎えていたのだから。
ハッと我に返ったのは、一通り歌い終わって「わー、おめでとー!」と満面の笑みを讃えた光一と成実、それから御堂にもパチパチと拍手されて、蝋燭を吹き消すのを催促された時だった。
三十本もの蝋燭を一息で吹き消せるのかといった疑問は当然、竜二の脳裏に浮かんだのだが。
期待に応えてこそ、祝ってくれた三人への恩を返せる。
これでもかとばかりに大きく息を吸い込んで、一気に吹き消してやった。
反動で大量の煙を吸い込みゲホゲホ咽る竜二に、三人は大喜びの大爆笑。
こうして楽しい雰囲気のまま、三十歳の誕生会は大いに盛り上がったのであった。
おしまい