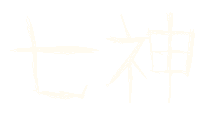act4-2 初夜
ひとしきり泣いて興奮も収まった頃に、背を押されて部屋を出る。マッド=フライヤーと名乗る黒人士官に連れられて入ったのは、取調室だった。
右を向いても左を向いても、オレンジの制服に身を包んだ連邦軍兵士ばかりである。
しかし、シンは孤独ではない。
傍らにはマダムの姿がある。
不安は少し、和らいだ。
「さて、名前は――シン=トウガ君だったね?」
奨められた席へ腰掛けながら、マッドの問いにシンが頷く。
「はい」
「宜しい。では、トウガ君。君に二、三、質問がある」
「何ですか?」と尋ねたものの、聞かれることは大いに予想できた。
何しろ連中には、ユニウスクラウニのアッシュと一緒にいたところを目撃されている。
当然この軍人が聞きたいのも、ユニウスクラウニに関することだろう。
仲間を売るつもりは、ない。
だが質問の内容如何によってはチャンスだと、シンは考えた。
連邦軍と能力者との戦いを、自分の返答次第で和解させられるかもしれない。
ギィッと軋む椅子を前に進めて、マッドが問う。
「君はユニウスクラウニの主要人物、アッシュ=ロードと行動を共にしていたな。彼と出会ったのは、いつだ?」
間をおかず、シンが答える。
「あ、えっと、俺の世界です。海で、迷子になった彼と出会って」
「迷子?」
怪訝に眉を潜めたマッドは部下らしき女性と小声で話した後、すぐにシンへと向き直る。
「その時、アッシュは一人だったのか?」
「はい」
「ふむ……」
マッドは考え込んでいる。
予想していた答えと違ったのだろうか。
ややあって、次を促した。
「では、次の質問だ。君は、この世界について、どのような情報を与えられている?」
今度も迷わずシンは即答した。
「能力者と、そうでない人が戦っていて……戦争になっているって聞きました。連邦軍の人達が能力者を殺すから、だから武器を取って戦うしかないんだって、アッシュが言っていました」
マダムが、何か言いたげな顔をした。
彼女の様子を意識しながらシンは続ける。
「でも、これはアッシュから見た意見ですよね?連邦軍から見れば、能力者の持つ能力が皆を脅かすという理由で戦っているんですよね」
この意見には驚いたようで、マッドも他の士官も目を丸くしてシンを見つめている。
ユニウスクラウニと同行していた能力者だから、連邦軍を憎んでいるのだとばかり思われていたのだろう。
それは、当然だ。
シンだってリュウに諭されるまでは、本気で連邦軍を憎んだりもしてみた。
憎まなければ、やっていられなかったのだ。
マダムも両親も、皆、死んでしまったと言われ、途方に暮れていた。
何で、こんな事になったのか。
自分の世界で起きた、連邦軍とユニウスクラウニの衝突。
あれが悪いのか、あれのせいかと、激しく憤りもした。
かといって目の前のアッシュに怒りをぶつけるのは、少々ためらわれる。
彼も次元崩壊の原因の一つだが、同時に彼はシンを助けてくれた人物でもあった。
だからシンは見えぬ敵である連邦軍を憎むことで、寂しさや悲しみと戦った。
だが、今は違う。
マダムだけでも生きていた。
リュウから教えてもらった情報だってある。
誰かを憎むのは、もう終わりにしよう。
ニーナとゾナを殺した連邦軍の誰かを許すわけじゃない。
連邦軍の兵士を片っ端から殺したアッシュにしても、同じだ。
人を殺したという罪は絶対に許さないし、認めない。
ただ、それで相手を憎むのではなく、過ちを止める側に専念する。
これ以上、自分の目の前で誰かが殺されるのだけは絶対に止めてやる。
再び部下と小声で遣り取りしていたマッドがシンを、じっと見据える。
「君は、ユニウスクラウニに所属しているわけではないのか?」
間髪入れず、シンは頷いた。
「はい」
「では何故、アッシュと行動を共にしていたんだ?」
「彼が、俺を助けてくれたからです」
正確に言うと、次元の崩壊からシンを助けたのはアッシュではない。
だがアッシュは、異世界に放り出されて心細くなっていたシンに優しくしてくれた。
彼の明るさに、シンの心は救われたのだ。
「君はジンに」と言いかけて、マッドが言葉を改める。
「あぁ、ジンというのは、そこの元気特尉の事だが、彼に『殺すのはよくない』と言ったそうだな」
黒髪の少年、今は仏頂面で立っている彼を指さした。
シンも彼を一瞥し、頷いた。
「はい」
アッシュと戦った少年だ。
顔に見覚えがある。彼がジンか。
マッドも頷き、続けてシンに尋ねた。
「聞けばアッシュも大量に死者を出している。この件について、君はどう思っている?」
これこそ、待ちに待っていた質問だ。
真っ直ぐマッドを見つめて、シンは答えた。
「よくないと思っています」
「どういう風に?」
「人を殺すのが、です。たとえ敵対している相手だとしても、殺す必要なんてないはずです」
「ふむ、まぁ、理想ではそうだが……」
マッドは歯切れ悪く呟き、しかし、と反論に出た。
「現実問題として、能力者は能力という武で反乱を起こしている。もはや、理想だけでは収拾のつかない状態にある。それについては、どう思う?」
「やめればいいんだと思います」
意味が通じなかったのか、マッドがオウム返しに尋ね返す。
「やめればいい?」
「はい。戦うのをやめて、能力者を人間として扱ってあげて下さい」
戦いを始めたのは、どちらが先か――なんてのは、ささいな問題であろう。
重要なのは、連邦軍が能力者を同じ人間として扱っていない点だ。
虫けらのように扱い武力でねじ伏せるやり方では、反発を呼ぶだけである。
「それが出来れば、な」
苦々しく、マッドが呟く。
シンは、すかさず聞き返した。
「何故できないんですか?同じ人間でしょう、言葉だって通じる」
「シン」
背後から、マダムが我慢できないといった風に口を挟んできた。
「シン、それはもう無理よ。彼らは聞く耳を持っていないわ」
穏やかな彼女らしからぬ意見に、ついついシンの声も裏返る。
「どうして?どうして、そんな風に決めつけるんですか!」
「落ち着いて、シン」と、彼女は言った。
「私もモニター越しに戦場を見せてもらったけれど、酷いものだったわ。連邦軍の若い兵士が、能力者に襲われて殺されたの。それも一人だけじゃないわ、何人もの人が殺された。彼らは連邦軍の兵士を見つけ次第、次々と襲いかかってきて……交渉も確認もなしに、よ」
マダムは目を瞑ると、両手で肩を抱きしめた。
肩が、細かに震えている。よほど恐ろしい光景でも見たに違いない。
「でも、それは連邦軍が、そうだからですよ!連邦軍が能力者を殺すから、だから彼らも追い詰められてッ」
興奮するシンを、マッドも宥める。
「今さら卵と鶏論争を蒸し返すつもりはない。君の言いたいことも判らないではないが、既に交渉できる状態ではないんだ」
そうでなくても上からは、ひっきりなしに能力者抹殺命令が下ってくる。
和解なんて生ぬるい作戦が、今さら通るとも思えない。
死ぬか、殺すか。
生き延びるか、殺されるか。
両者の仲は、そこまでに達していた。
交渉するなどと言ったところで、向こうだって信じまい。
罠だと思うに決まっている。
本音を言うなればマッドだって、できることなら戦いなど、さっさと終わらせてしまいたい。
だが、どうやって対談の場を設けるか?
それを考えると頭の痛い話であった。
交渉を申し込むなら、相手もリーダークラスじゃないと話にならないだろう。
ユニウスクラウニのリーダーは、名前も判明していない正体不明の人物だ。
下っ端連中を捕らえたところで、何の手がかりも得られまい。
やはり捕らえるなら、ブラックリストに名を連ねるぐらいの大物でないと。
「君の処遇は、まだ決まっていない。もし、君が望むなら」
マッドの視線がマダムを一瞥する。
「そちらの女性と一緒に住む家を求める権利が、君には与えられている」
しかし、とも彼は言った。
「我々としては、能力者である君に協力してもらえるのが一番好ましいんだがね」
真っ向からマッドを見つめ返し、シンも尋ねる。
「協力って、何のですか?」
マッドは即答した。
「能力者との戦闘に、だよ。君の一番望む和解交渉は無理かもしれんが、殺さないでくれという頼みは実現できるかもしれん。君の持つ、あの能力さえ使えれば」
シンの持つ『凝固』の能力を、連邦軍が欲している。
生き物を凍らせても殺しはしない。
生きたまま相手を捕獲するには、もっともうってつけの能力だ。
「君の能力について教えてもらいたい。範囲は、どれほどだ?そして最大で何人まで凍らせられる?」
「ま、待って下さい」
次々に質問を浴びせてくるマッドに手でストップをかけ、シンは正直に暴露する。
すなわち己の能力が、自分の意志で思った通りに発動させられるわけではないということを。
「シン……あなた、一体……能力って、何の話なの?」
背後で、マダムが小さく呟く。
彼女を脅えさせた能力者の能力をシンも持っているという事実が、信じられないようだ。
まぁ、本人だって未だに信じられないのだから、無理もない。
マダムの不安を極力刺激しないよう、落ち着いた口調でシンは言った。
「海の怪物をやっつけた力の事なら、俺はまだ……使いこなせているとは言えません。もし俺が、その力を使いこなせていたんなら、俺はきっと誰にも人を殺させなかった」
「そうだな」と割合素直にマッドも頷き、シンとマダムを交互に見やる。
「君は自分の能力を使いこなしたいかね?それとも、二度と使えないよう封印してしまいたいか」
使いこなせるものなら、使いこなしたい。
しかし、そうだと答えるのは、自分を能力者と認めるも同然である。
異様な力を身につけたシンのことをマダムは、どう思ったのだろうか?
恐る恐るシンが彼女を振り返ると、マダムは無言で頷いた。
シンが、そうと決めたのなら、そうすればいい。
そのほうが、きっとシン自身の為になる。
彼女の眼差しは、そう言っているようにも見えた。
もう一度マッドへ向き直り、シンは強く頷く。
「はい。俺の力で、どこまで出来るか判らないけど、戦いを止めたいんです。殺さなくても戦いを終わらせることができるってのを、証明したいんです」
言い切った直後、マッドの背後に立つ女性士官が微かに眉を潜めたのに気づく。
また甘言を、と思われたのだろう。
だが、甘ちゃんだと罵られても構わない。
殺さなくても、戦いは終わらせられる。
両者が戦いを捨てれば、殺し合いもやめられる。
自分で考え出した、この素晴らしいアイディアを改める気など、シンには全くなかった。
「君の意気込みは、よく判った。では本日付で、君は特務七神に配属される」
とくむ、ななかみ。
リュウの言っていた部署名だ。
マッドの言葉を脳裏で繰り返しながら、シンは頷く。
マッドも頷き返し、シンへ微笑む。
「さっそくだが、特務七神には任務が下っている。メンバーが整い次第、北欧区域へ能力者の鎮圧に向かってくれとの事だ」
北欧区域というのも、リュウの話に出てきた場所である。
さすが運命の先を見透かす男、彼の予測には一寸たりとも狂いがない。
「神崎特尉の精神状態も正常に戻ったという報告を受けている。よって特務七神は明朝九時に本部を出発。全員で北欧区域へ向かう」
黒人士官の命令を半ば聞き流しながら、シンはリュウのことを考えた。
北欧区域で、無事に彼と合流できますように。
シンが連邦軍に連れ去られてからの一週間。
ユニウスクラウニとて、手をこまねいてばかりだったわけではない。
彼らは一旦、南米基地の奪還を諦めて、アジア区域と北欧区域に兵力を集めていた。
だが、その中にアッシュの姿は、見あたらなかった。
シンの奪回を諦めた訳じゃない。
度重なる失態を元に、本拠で謹慎処分を受けていただけだ。
その間も、仲間からは逐一報告が入ってくる。
南米基地の連邦軍が増兵されただとか、アジア区域にも強力な能力者兵士がいただのと。
もはや連邦軍に味方する能力者の存在は、ユニウスクラウニ全てのメンバーが知る処となっていた。
アッシュが対戦した一人。
そいつと一緒に、もう一人、仲間がいた。
さらにアジア区域と北欧でも、四人ほど確認されている。
たかが一桁数といえど、油断できない。
目撃した数以上いる可能性だってある。
平凡な人間に協力する裏切り者がいたというだけでも、衝撃だった。
シンの行方は完全に判らなくなっていた。
アジアで見かけたという噂もあれば、北欧で見たという情報もある。
どちらも現地で探したメンバーからは発見の報告がない。
否、シンが何処かへ幽閉されるとすれば、それは連邦軍の本部以外に考えられなかった。
連邦軍の女兵士が言っていたではないか。
シンは連邦軍が保護すると。
アッシュでさえも簡単に乗り込めない場所に、監禁されてしまったのだ。
保護すると宣言した以上、彼は殺されていないだろう。
もし殺すつもりだったというのなら、何故あの時に殺さなかった?
凍りついたシンは身動き一つできなかったのだから、殺そうと思えば殺せたはずだ。
アイアンやシンが言っていたように、仲間を助けるために協力を強制される。
そういうことだって、あり得る。
シンは正式なユニウスクラウニのメンバーではないのだし。
早まって彼がおかしな行動に出ていないことを、アッシュは祈った。
アッシュが謹慎しているなど、つゆ知らず、南米基地では降下部隊所属のアヤが、彼の到着を今か今かと待ち続けていた。
だがマリヤ中尉や兵士の不安など、どこ吹く風で、今のところ能力者の襲撃など数える程度しかない。
いずれも小規模ゲリラばかりで、ユニウスクラウニ級の強力な能力者は一人も訪れなかった。
「彼らは基地奪還を諦めてしまったのでしょうか?」
アヤの問いに、南米基地の管理を預かるマリヤが答えた。
「判らん。だが他地区では襲撃の報告もある。一旦休止しているだけだろう、警戒は怠るな」
彼女に言われるまでもない。
ユニウスクラウニから奪い取って以来、この基地は常に厳戒態勢を強いられている。
四人の能力者に襲撃を受け一時は奪回されかかったが、セブンゴッドのおかげで何とか持ち直した。
セブンゴッド――連邦軍内部では特務七神とも呼ばれている。
マッド=フライヤー大尉率いる特殊部隊だ。
メンバーは全て、能力者で構成されている。
能力者が連邦軍に味方するなど世間一般の常識では、およそ考えられない事態だろう。
彼らは肉親を守るために入隊したという噂であった。
能力者狩りから守ってくれた肉親への、恩返しというわけか。
ならば彼らが連邦軍を裏切ることは、万が一にもあり得ない。
裏切れば、肉親は殺される。
子供でも判る結果だ。
そのセブンゴッドのメンバーが二名派遣され、見事、四人の能力者を打ち倒してくれたのである。
アヤ達補充兵士は基地へ到着した直後、大掃除を任された。
基地に山高く積もった謎の灰を、森へ捨ててこいという命令であった。
灰の正体が何であるか。
あとで他の兵士から聞かされた時、改めて能力者の力を嫌悪すると同時に、アッシュの脳天気な顔が脳裏に浮かぶ。
自分の幼なじみは大罪者だった。
アヤの予感ではアッシュは必ず、もう一度、この基地を攻めてくる。
ユニウスクラウニが、基地をこのままにしておくとは思えない。
そして作戦を実行するなら、名誉挽回としてアッシュを向かわせるはずだ。
大罪を償うには、もはや死刑しか残されていない。
アッシュへ死刑を執行するのは、幼なじみで顔馴染みの自分がやってやろう。
それが彼に対する、せめてもの情けになると考えて。
特務七神への配属が決まり、シンとマダムは取調室からも解放される。
それぞれ別の個室が与えられ、ひとまず二人はシンの部屋に落ち着いた。
「本当に、驚いたわ。あなたが生きていたなんて」
紅茶を煎れ、マダムがシンの前にカップを置く。
シンをじっと見つめ、瞳に歓喜の色を浮かべた。
照れて頭を掻きながら、シンも彼女を見つめ返す。
「俺だって、驚きましたよ。マダム……生きてて、良かったです。ホントに」
カップを手に取り、一口すすった。
紛れもなくマダムの煎れた紅茶だ。
「どこで、何をしていたの?ユニウスクラウニとかいう、組織にいたの?」
「はい。マダムは……連邦軍に?」
互いに、これまでの経緯を語り合い、やがて能力者の話題へと移ってゆく。
「マッド大尉は、あなたを能力者だとおっしゃっていたわね。……本当なの?」
口調は穏やかだが、マダムの手は微かに震えている。
カップと皿が触れあって、カチャカチャと小さな音を立てた。
飲み終えたカップをテーブルに置き、シンは頷いた。
「えぇ、俺自身も信じられないんですが……そうみたいです」
「そう、みたい?」
怪訝に尋ね返す彼女へ思案顔で頷くと、シンは一言一言、記憶の中から言葉を探す。
海の怪物と戦った時に、掌へ感じた謎の冷たさ。
掌で生まれた小さな氷の刃。
「俺にも、よく判らないんです。ちゃんと制御できるわけじゃないですし」
氷の刃を握りしめ、怪物へ投げつけた。
海は瞬く間に凍りつき、怪物の動きを止めた。
ただ、凍りついたのは怪物と、その周辺の水だけで、シンの墜落した付近の水が凍ったのは、水面だけであった。
凍りつくのは相当狭い範囲に限られているらしい。
「そう……あの怪物を、あなたは倒したのね」
マダムが溜息をつく。優しい目でシンを讃えた。
「おめでとう、シン」
「え……あ……っ、ありがとうございます!」
思いがけない祝福にシンの頬は真っ赤に染まり、上擦った声で敬礼する。
緊張でガチガチな彼を見て、マダムが苦笑した。
「まぁ、シンったら。あなたは偉業を成し遂げた、勇者ですもの。もっと誇らしげにしてもいいのよ?」
今だ。
言うなら、今しかない。
マダムに認められた、今なら好きだと言っても驚かれたりしないはずだ。
「本当なら、何かお祝いしてあげたいところだけど」と続けるマダムの言葉を、シンは大声で遮った。
「すっ、好きです!マダム!好きですッッ!!」
真っ赤に顔を染めあげたまま額には汗をかき、両眼を瞑って絶叫した。
思春期の子供だって、もう少しマシな告白をするんじゃなかろうか。
シンの唐突な告白にマダムは、きょとんと目を丸くしていたが、やがて穏やかに微笑んだ。
「えぇ、私も好きよ。シン、あなたのことが。これからも、ずっと一緒にいてちょうだいね」
「はッ、はいッッッ!!」
先ほどよりも倍は緊張に震えながら、シンは直立不動の姿勢で何度も頷く。
好きの意味合いが少々食い違っているような気がした。
だが、文句は言うまい。
マダムが生きていた。
これからも一緒に居られる。
それだけで、シンは幸せの絶頂にあった。
「……あ、そうだ」
幸せに浸っていたシンは、ふと我に返る。
「俺は特務七神と同行しますが、マダムはどうするんですか?」
マッド大尉はシンの処遇については説明したが、マダムについては一言も説明しなかった。
これからも一緒でいようと約束したのだから、当然シンとしてはマダムも一緒に連れて行きたい。
しかし――
戦場になると判っている場所へマダムを連れて行くというのは、どうなんだとも自問する。
もし流れ弾に当たって彼女が死ぬような事でもあれば、シンはきっと一生自分を許せないだろう。
悶々と悩むシンを前に、マダムが答えた。
「ここに残って、あなたの帰りを待ちます」
「必ず帰ってきます」
頷くシンへ、一本の指が差し出される。
「約束よ」
「はい」
マダムの差し出した小指に自分の小指を絡めて、シンは頷いた。
連邦軍の本部で目覚めてから、初の夜を明けた翌日、シンは特務七神と共に北欧地域へと飛び立った。