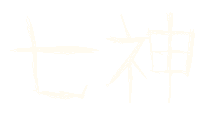act3-2 待ち伏せ
一通りクラウニフリードの内部を案内してもらったシンは、いよいよメンバーと対面する。といっても、この船にいるだけがユニウスクラウニの全員ではない。
アッシュが担当していた南米密林地帯以外に、アジア区域、北太平洋区域など、地上ポイントは多数存在する。
それらの拠点を防衛しているとの話だ。
拠点を守るメンバーは地域のゲリラと密着している。
地上の何処かで何かが起これば、即座にクラウニフリードへも連絡が飛ぶ手はずになっていた。
「能力者のネットワークは年々固まってきてるんだけどぉ」
アッシュの説明は覇気がない。
「でも連邦軍は、それ以上のネットワークを持っているからね。なかなか上手くいかないんだ」
地球に住む八十パーセント以上の人間が、能力を持たぬ者だという。
アッシュ達は、それらを敵に回して戦っているのだ。
人数で見ると非常に不利な戦いである。
「あたし達、一人一人は、まぁそれなりに強いと思うんだけど」と、これは栗毛の少女アユラ。
彼女は肩をすくめ、小さくぼやいた。
「向こうは人海戦術でくるからね。こっちも人間だし、長期戦になったらオシマイってわけ」
いくら化け物じみた力があるといっても、体力は無尽蔵ではない。
次々に手数を送り込まれてくれば、精神体力共に消耗を強いられ、戦闘不能に追い込まれるのは必至である。
それに、生まれてくる数の違いもある。
向こうは出産で幾らでも増やせるだろうが、こちらは偶然に頼るしかないのだ。
元々は同じ種族だというのに、生まれた時に人と違う力を持っていたというだけで根絶やしにする。
能力者から人権を奪う権利が、連邦軍のどこにあるというのか。
数に任せた暴力で追い込まれて、だから仕方なく能力者は戦う決意をかためた。
それは生き物として当然の行動だと思う。
自分達の生活の為だけに、能力者を排除しようとする連邦軍のエゴには吐き気がする。
だが、もし、数の絶対比が逆だとしたら――?
背中に薄ら寒いものを感じたシンは、ぶるっと身を震わせ、アッシュを見た。
もし能力者より非能力者のほうが少なかったとしたら、アッシュ達は非能力者を根絶やしにしていたのだろうか。
力のない者は異端だとして、皆殺しにしていた……?
「ん?なぁに、シンー」
無邪気な笑顔でアッシュが尋ねてきた。
シンは無理に笑顔を浮かべて、取り繕う。
「い、いや、何でもない」
「もしかして、寒いの?暖房、つけてこようっか」
気を利かせてくれるアッシュに首を振り、シンは、それとなく他のメンバーを見渡した。
クラウニフリードは空中要塞と呼べるほどの大きさを誇る飛行船だが、搭乗員は、それほど多くない。
総勢二十五名。
昔と違い、今はボタン一つで自動操縦のできる時代だ。
今は二十五名中の二十人が、この部屋に集められている。
アッシュが集合をかけた。
背の高い男性が、ロナルド。
髪の長い、紫の髪の毛をした女性。
彼女はヴィオラと名乗った。
黒髪で中肉中背の青年は、オハラというらしい。
尾っぽの尾に、野原の原だと説明された。
ニレンジ、シャラ、ココルコの三人は、まだ幼い子供だ。
子供といえば、アッシュの傍らにいる栗毛のアユラも幼い。
十歳か、そこらに見える。
取り立てて特徴のないブロンド、あえて言うなら鼻がやや大きい青年。
彼の名は、スミス。
シンよりも黒い肌の持ち主、丸太棒のような腕をした男性はガルシアと名乗りをあげた。
緑色の髪の毛を後ろで一つに縛っているのは、マレイジア。
綺麗な髪ですねと喜ぶシンへ彼女は、そう言ってくれるのは能力者の方だけですと寂しげに笑った。
不思議な色の髪を持つメンバーは、他にもいる。
そばかすだらけの少女、ニーナ。
気の強そうな男の子、クィッキー。
この二人は、共に薄い桃色がかった髪をしている。
ニーナのピンクは綺麗だが、クィッキーの髪は、どう見ても似合っていない。
きっと本人も、気にしているのであろう。
シンがマレイジアの髪を褒めた時、彼の眉毛がピクッと神経質に跳ね上がったのを見た。
だからシンは、あえて彼のピンク色には突っ込まずに流しておいた。
そのお隣、非常に顔の似通った二人の少女。
これは双子だろうか。
ただでさえ顔が似ているのに、髪型まで同じ三つ編みにしているもんだから余計見分けがつかない。
彼女達は同時に頭を下げて、ミユですミィですと名乗った。
黒服に身を包んだスマートな男性はクロトとだけ名乗り、そっぽを向いてしまう。
アッシュに怒られても、彼はシンのほうを見ようとしなかった。
極度の恥ずかしがり屋か、あるいは人見知りするタイプなのかもしれない。
それとは逆に、やたら熱い視線をシンに送ってくる奴もいる。
筋肉質の男性アイアンが、そうだ。
黙ってジッと眺めては時折熱い溜息をついており、これも話しかけにくい人物ではある。
帽子を目深に被り、壁に背を持たれかけた青年が、ひょいっと会釈する。
ゾナというのが、彼の名だ。
残る二人は先ほどから窓の外ばかり眺めていて、アッシュが自己紹介しろと促しても平然と無視している。
仕方なくアユラが紹介したところによると、やせて小柄なほうがサム。
太って大柄なほうが、トム。
二人は兄弟だが、トムのほうが兄かと思いきや実は弟であるらしい。
この二十名に、リーガル、エリス、サリーナ、ジャッカル、アンナの五名を加えたメンバー。
それが今、この船に乗っている全員である。
それぞれの能力は詳しく聞かなかった。
一緒に戦ううちに判るわよ、とはアユラの弁である。
ただね、とも彼女は付け加えた。
「皆が皆、戦える力を持ってる訳じゃないから。例えばサリーナなんか、戦場に出たら五秒で即死決定ね。だからさ、戦える力を持ってる奴は戦えない奴の分も頑張らないといけないってワケ」
「そうだとも。だから、君には期待しているんだ」
両手を握りしめ、ロナルドが言う。
「アッシュから聞いたよ。君は海を凍らせる力を持っているんだってね」
どんな風に話したのか、ロナルドの目はきらきらと輝いており並々ならぬ期待を感じる。
その力が、いつ何処でも発動すればね……と思いながら、シンは曖昧に頷いた。
未だに判らない。
自分が本当に能力者と呼ばれる人間と同じなのか、どうかが。
だが、たとえ能力がなかったとしても、シンはアッシュ達に荷担しようと心に決めていた。
己のエゴで同じ種族、同じ人間を虐殺しようとする連邦軍だけは、どうしても信用出来なかったからだ。
「さて、と。それじゃ自己紹介も済んだことだし、あたし、もう行くね?」
不意に背中を向けたのは、ニーナ。
彼女の背中に噴射機を見つけて、シンが尋ねる。
「どこへ行くんだ?」
「南米基地。アッシュが放り出しちゃったせいで、あそこ占領されちゃったのよ。連邦軍に」
アッシュが何か言うよりも早く、アユラが甲高い声で騒ぎたてる。
「また、そういう言い方する!しょうがないじゃない、緊急招集かけたのはリーガルなんだからァ」
「それはそうだけど、でも誰か一人、代わりに置いていくのは基本でしょ」とニーナは、すげない。
「二人とも来る必要なんてなかったんだから。アッシュが来るなら、アユラ、あなたは残ればよかったのよ」
それにしても、アッシュとアユラが抜けただけで、簡単に占領されたというのも解せない話だ。
基地というぐらいだから、彼らの他にも能力持ちの雑兵が何名か残っていたはずである。
シンが尋ねるとニーナは緩く首を振り、「ガス兵器って知ってる?」と逆に尋ね返してきた。
「連邦軍の奴らってね、雑兵が相手だと途端に強気になるのよね。アッシュとアユラがいなくなったのを確認してから、基地にガスを撒いたの。もちろんガスってのは、毒ガスよ」
「毒ガスだって!?」
叫んだのはシンだけではない。
ガルシアにアイアン、スミスも顔色を変えた。
震える声でスミスが呟く。
「ひ、酷い……それじゃ、あの基地にいた六十人は」
「えぇ。全滅よ」
答えるニーナは、淡々としている。
だが彼女の両手が、しっかりと握られ、小刻みに震えているのをシンは見た。
「連邦軍も、ついに本腰を入れてきたって事か」
ゾナが呟く。
ニーナは、またも頷き、彼を見た。
「えぇ、南米支部を占領するにあたり、雑兵の消耗は激しかったから。ここまでの強硬手段に出たのは、アッシュがいないと確信できたおかげでしょうけれど」
「アッシュが?」
シンは、それも不思議に思い、本人へ尋ねた。
「アッシュ。君は、毒ガスが効かない体質なのか?」
「うぅん?」とアッシュは即座に首を振り、小首をかしげる。
「効くよ。何で?」
ニーナは苦笑した。
「まともに吸えば、アッシュだって死んじゃうわよ。ただ彼に炎を使われたらガスに引火して、中でガスを撒いている人達が逃げられなくなるでしょ?」
「でも、連邦軍の兵士は人海戦術だってアユラが」
首をかしげるシンへ、ニーナが答える。
「いくら捨て駒でも、その程度で切り捨てていったら人がいなくなっちゃうわ。危険な任務に志願する人は希少価値だから、大切に扱わなくっちゃね」
二人の会話に割り込んだのは、ガルシアだ。
暗い目でニーナに問う。
「――で、連邦軍の、どこの部隊だ?俺達の留守を見計らって乗っ取りを強行したのは」
それに応えたのは、オハラである。
「そりゃ決まってる、飛行降下部隊だよ。あの部隊は執拗に南米基地を狙っていたしね」
「飛行降下部隊ィィ!?」
アッシュが素っ頓狂な声を張り上げる。
「チックショー、俺がいないと判ってて狙うなんて!ひきょーものぉぉ〜っ!!」
悔しさに地団駄踏む彼を横目に、シンはオハラへ、ひそひそと尋ねた。
「どうして連邦軍の人達は、アッシュが基地にいないと判ったのかな?」
「我々にも不思議なんだ」
オハラは腕を組み、天井を睨みつけた。
「奴らが、どうやって基地内部の事情を知り得たのか」
「……もしかしたら、スパイがいるのかもしれない」
ぽつりと呟いた人物へ、一斉に皆の目が向けられる。
呟いたのはクロトだ。
「連邦軍に情報を横流しする能力者がいるだと?ふん、馬鹿馬鹿しい」
すぐにガルシアが視線を外し、オハラも大きく肩で落胆の息をつく。
「ありえないな。我々能力者が連邦軍に味方して、何の見返りがあるというんだ?」
クロトは答えなかったが、シンには、すぐに判った。
見返りは自分の命だ。
能力者だって、能力のない者と同じ人間なのである。
命と引き替えに情報をよこせ。
そう言われたら、情報をリークしてしまっても仕方がない。
誰だって死にたくはない。
いつまで経ってもクロトが答えないので、ニーナは肩をすくめて踵を返す。
「とにかく。そういうわけで、行ってくるわね」
「大丈夫なのか?」
相手はガスを使うような相手なのにと心配するシンへ向けて、彼女は背中越しに微笑む。
「大丈夫よ。今度は向こうが基地に陣取っているんだもの、毒ガスは使われないわ」
「いってらっしゃ〜い」
アユラが気のない送り返事をし、アッシュは力一杯手を振って見送った。
「ニーナ、俺の分まで戦ってくれよな!」
「ハイハイ」
これまた気のない返事を最後に、ニーナは出て行った。
――これが彼女との最後の会話になるとは、この時は誰もが予想していなかった。
11:24 毒ガス散布
18:31 一部生存反応の見られる兵士を焼却
20:57 全滅を確認
21:02 作戦完了
「酷いな……これは。生き残りを焼いただと?」
病室のベッドの上で、マッドが唸る。
かつて自分の指揮していた飛行降下部隊が、ユニウスクラウニの南米基地を制圧した。
そこまでは、いい。
問題は、そのやり方だ。
毒ガスを散布したと資料に書かれていて、彼は青ざめた。
ガスと核だけは絶対に使っては、いけない。
それが、大昔の戦争で得た教訓ではなかったのか。
ガスなど撒けば、一帯の生態にも影響を及ぼす。
それ以前に、人間相手に毒ガスを使うなど正気の沙汰ではない。
「仕方ないわ。上層部が判断を下したのだもの」
ぽつりとアリスが呟く。
この資料を、彼女がマッドの元へ持ってきた。
「ガスなど撒かずとも、あの基地は制圧できたはずだ!」
思わず声を荒げるマッドを一瞥し、アリスは淡々と言い返す。
「あなたのやり方では制圧できない。と、上の連中は考えたのね」
人海戦術で失った部下の数は、何人だ?
何十人、という被害だったはずだ。
別に、マッドが無能な指揮官だったと言いたいわけではない。
ジャングルの中にあるような基地だ、兵士を空から送り込んで攻めるという戦法は悪くない。
というよりも普通の人間ならば誰でも、そういった戦法を選ぶ。
だが上の連中は最も効率的で、最も非人道的な作戦を取った。
ミサイルを飛ばさなかったのは、基地を再利用する算段があったのだろう。
現に今は飛行部隊の兵士が、基地を占領している。
かつての部下の顔を思い浮かべ、マッドは何度も首を振った。
彼らが、この作戦に参加したのか。
毒ガスを撒いて、能力者を虫けらのように殺したのか。
戦争をしている以上、誰もが人殺しである。
そのことを正当化するつもりはない。
しかし、やってはいけない戦い方というのは彼らの中にも存在する。
ガスを使うなど虐殺行為でしかない。
これでは、能力者狩りの時代に逆戻りしたも同然だ。
「正々堂々と戦いたかったのね」
苦悩する彼を見つめて、アリスがポツンと呟いた。
「でも、これは戦争だから。多く生き残った方が勝つの。その為には手段を選んでいられない」
彼女の言うとおりだ。
マッドが顔をあげると、じっと見つめるアリスと目があった。
「私、一度聞いてみたかった」
「……何を?」
彼女は、ひたとマッドを真っ向から見据えて尋ねた。
「あなたは、どうして連邦軍に入ったの?どうして、能力者を倒そうと思ったの」
アリスの場合は家族の命と引き替えに、軍へ放り込まれた。
いわば生け贄だ。
拒もうと思えば拒めたかもしれないが、彼女は素直に軍入りした。
同じ能力者を殺す、そのことに対しても割り切っている。
彼らは私と同じではない。
それが、彼女の出した答えだ。
むしろ彼らが連邦軍に逆らうせいで、世間の能力者への評価が厳しくなったのだと考えている。
おとなしく連邦軍の飼い犬になっておけばいい。
そうすれば、もう、誰も殺されない。
マッドが、ふぅっと大きく息を吐いて、アリスを見つめ返す。
「能力者に、肉親を殺された。入隊したのは敵討ちが目的だった。……正義心じゃない」
能力者狩りの誤爆と能力者によるゲリラが結成されつつある、混沌とした時代だった。
フライヤー一家は、ごく普通の家庭だったのだが、ゲリラと能力者狩りの戦闘に巻き込まれた。
戦いは突如として街角で始まり、ゲリラ側の自爆テロに巻き込まれて父親が死亡。
翌年には兄と母が能力者狩りの誤認で捕まり、護送される途中でゲリラに襲われ死んだ。
不幸な事故として諦めてしまえば、よかったのかもしれない。
しかし十五歳の血気盛んな若者に、それを強制するのは無理であった。
憎しみに燃えるマッドは連邦軍に入隊し、死体の山と共に昇進を重ねた。
死ぬのは怖くない。
人を殺すのも、怖くなかった。
「今は、どうなの?まだ……能力者を憎んでいるの?」
「いや……」
緩く首を振り、マッドはシーツに目を落とした。
立ち止まったのは、下に部下を抱える身分となった時だ。
命を預かる。
その任務の重さと命の重みに、ようやく彼は気がついた。
自分も能力者狩りの連中と同じ事をしているという事に気づいたのも、その頃だ。
それについて悩みもしたが、全てが遅すぎた。
彼の手は血にまみれていた。
あまりにも多くの能力者を殺しすぎた。
組織として、そして人間としても、後戻りできない場所に立っていた。
「能力者を憎んではいない……だが連邦軍の兵士として、任務を放棄するわけにはいかない」
「軍をやめようとは、思わなかったの?」
率直な質問に、マッドは苦笑した。
「連邦軍が間違った方向に進めば、困るのは俺の家族のような一般人だ。それが判っているのに、軍を辞められると思うか?」
一般人を守るために、能力者を殺す。
それが本当に正しい行為なのかどうかは、マッドにも判らない。
だが連邦軍の結成と共に、能力者狩りという存在は消えた。
少なくとも連邦軍という存在が、誤爆による一般人の死亡を防いだことになる。
ならば、一般人を守るために連邦軍の兵士であり続ける。
それこそがマッドに課せられた使命ではないのか。
次第に彼は、そう考えるようになっていった。
「そう……人柱になるつもりなのね」
どことなく寂しげに呟かれ、だがマッドは、それを否定する。
「そういうつもりは、ない」
アリスが彼を見ると、力強い視線とぶつかった。
「俺は俺の信念を貫く為に、軍に残ると決めた」
「信念?」
「この命を、一般人を守る為に使おうという信念だ」
命を他人のために捨てるというのなら、やはり、それは人柱ではないか。
アリスが問うと、マッドは否定する。
「違う、誰かの犠牲になりたいわけじゃない。俺が出来ることを誰かの為に役立てたい。ただ、それだけなんだ。……人柱なんて格好いいもんじゃない。ただの自己満足だ」
コンコンと扉がノックされ、会話が途切れる。
アリスが立ち上がり、ドアを開けた。
「どうぞ」
入ってきた人物を見て、マッドが、あっという顔になる。
「失礼します。高峰アヤ、入ります」
病室を訪れたのは、飛行降下部隊所属の高峰アヤであった。
降下作戦中に行方不明となった彼女は、何故か遠く離れた孤島で発見、保護された。
神矢倉の報告によれば、彼女は能力者に拉致されていたらしい。
「フライヤー大尉、お久しぶりです。怪我をなされたと聞いておりましたけれど、お元気なようで何よりです」
「あぁ。君も、体調はどうだ?あれから、何ともないか?」
発見された当初は全身に打撲を負っており、足を骨折するなどの怪我も酷かった。
今、目の前に立つ彼女は、すっかり全快したようで元気な姿を見せている。
「えぇ、もう大丈夫です。もう少し発見が遅かったら、死んでいたかもしれませんが……フライヤー大尉の部下の方々のおかげで、命拾いしました」
「そうか。いや、君が無事に助かったと聞いた時はホッとした」
心底嬉しそうなマッドを見て、アヤはくすぐったそうに微笑むが、すぐに、その顔が曇るのを、アリスは横目に眺めた。
「でも、タツキさんは……」
「そうだな」と、マッドも表情を暗くして頷く。
「あの作戦では多くの者が亡くなった……俺のやり方が甘いと立証されたようなものだ」
ハッとした表情で、アヤが顔をあげる。
「大尉も毒ガス作戦の件を、お聞きになったのですか?」
「あぁ。資料で見た」
「……そうですか」
ちら、とアヤに横目で見られたので、アリスは会釈をしておく。
彼女は何の用で訪ねてきたのかを考えた。
アリスの視線には気づかず、アヤが話を進める。
「では降下部隊が現在、彼らの南米支部を占領しているのも、ご存じですね」
「あぁ」
僅かに微笑み、彼女は言った。
「なら、話も早くて助かります」
「話?」
怪訝に眉をひそめるマッドへ頷くと、高峰アヤは真っ直ぐ彼を見つめて報告する。
「降下部隊と特務七神で連携を組むという作戦を、お伝えに参りました」
連携と言ったが、正しくは協力要請だ。
戦える部下を差し出せ、という要求である。
基地の奪還を狙って、ユニウスクラウニが能力者を差し向けてくるのは必至だろう。
能力者の能力は個々によってピンキリだが、戦闘能力の高い者は銃器で包囲しても苦戦する。
今回制圧が成功したのだって、アッシュ=ロードとアユラ=マディッシュが留守にしていたからだ。
彼らがいたら、たとえ毒ガスを使ったとしても犠牲は大量に出たはずだ。
それ以前に、ガスなど使えなかった。
アッシュ=ロードは、炎を武器とする能力者なのだ。
ガスに炎は天敵だ。
能力者に対し、一般兵に相手をしろというのは酷な要求である。
今までに失敗してきた降下部隊兵士の数を見れば、一目瞭然であろう。
能力者の相手は、能力者にやらせればいい。
こういった事態のために、特務七神は存在しているようなものだ。
「――判った。では、こちらからは元気神と草壁神太郎を派遣しよう」
マッドの命令にアヤは頷くが、アリスが待ったをかける。
「待って」
「ん?どうした、アリス」
マッド、それからアヤの顔を交互に見てから、彼女は答えた。
「草壁くんの能力は、白兵戦には向かないわ。彼の代わりに、私が行く」
じぃっと見つめられ、マッドは視線を外す。
どうしたことか、彼女には逆らえない強い意志を感じた。
アヤも、じっとマッドを見つめている。
彼が、どう判断を下すのか待っているのだろう。
ややあって、マッドは命令を覆した。
「では、元気神と神崎アリスを送る。場所は現地へ直接――で、いいな?」
結局、彼はアリスの希望を尊重した。
アリスは黙って頷くと、先に出ていく。
判ったとも了解とも言わぬ横柄な態度に、アヤは反感を抱いた。
上司に敬意を払わぬとは、およそ軍人らしくもない。
「……いいんですか?部下のわがままを尊重してしまって」
なんとなく不機嫌そうなアヤの問いに、マッドは困惑の表情をシーツへ落とす。
「本人が行くと志願しているんだ。聞いてやるのも上司の努めだろう」
少々苦言かもしれないが、あえてアヤは言い返した。
「降下部隊を指揮していた頃と比べますと、大尉は弱気になったのではありませんか?」
マッドが弱気になるのには理由がある。
七神に属する部下が、どういった能力を持ち、どういった風に戦うのか、マッドには、それらが全然把握できていなかったのだ。