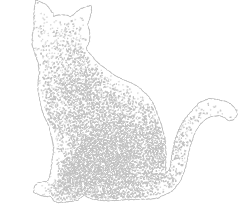怪盗キャットファイター
風花のお誕生日
貧乏生活が嫌で嫌で、だって誕生日なのに祝ってもらえないほど貧乏だなんて、嫌すぎない!?
だから、親元を離れた。後悔はしていない。
怪盗団が悪い組織だってのは知っていたけど、貧乏生活を抜け出せるんだったら何でもよかった。
身を寄せる場所は、どこだっていい。三食ご飯が食べられて、屋根と壁がある場所なら。
あたしは、幸せになりたかったんだ!
貧乏が嫌で家出した風花は、怪盗キャットファイターへ入団した。
地下に潜り込んでいるが、一応、三食屋根壁つきのアジトである。
欲しいものは盗んで奪い取る。
警官に捕まらない限り、裕福な人生が約束された。
仕事着が恥ずかしい点を除けば、快適な暮らしと言えよう。
カレンダーを眺めて、ふと気づく。今日は自分の誕生日じゃないか。
ここへ来たばかりの頃、悠平が盛大に祝ってくれたのを思い出す。
生まれてはじめて食べたバースデーケーキは、半分涙の味がした。
人間って嬉しい時にも涙が出るんだと、この日風花は初めて知った。
そればかりじゃない。プレゼントと称して、メンバーの皆が色々な物をくれた。
もらったものは全部宝箱に入れて保管してある。
時折取り出して眺めながら、嬉しかった誕生日を思い出すのが彼女の趣味になった。
それから毎年、皆は誕生日を祝ってくれる。
もちろん風花もメンバーの誕生日を祝い、皆のセンスを参考にプレゼントを贈ってやった。
全部盗品だから、お互い損なしの満足なプレゼントだ。
去年は龍輔がキャットファイターへ入ってきた。
入って直後の誕生日会だったというのに、彼もきっちり風花にプレゼントをよこしてきた。
そこんとこは、さすが大人だなぁと感心したのだが、彼のプレゼントは真っ赤なドレスで、こんなの休日でも着れそうにない。
タンスにしまいこんで、それっきりだ。
他の皆みたいにアクセサリーや小物雑貨をくれたなら、宝箱にも入って眺めることが出来たのに。
へんなところで気が利かない大人だ。
今年こそ、いいものをくれるといいんだけど。
怪盗団で贅沢に味をしめてからというもの、すっかり増長してしまった風花であった……
「風花ちゃん、十六の誕生日おめでと〜!」
パンパン!とクラッカーが弾けてテープが飛び交う。
「十六っていやぁ、おめぇ、お嫁さんだぞ。お嫁さんになれる歳じゃねぇか。まぁ、こんな穴蔵怪盗団にいたんじゃよ、嫁の貰い手もねぇかぁ、ガッハッハ!」
酒も入っていないのに、悠平はすっかり出来上がっている。
怪盗団は子供ばかりだから、飲み物はノンアルコール。しらふで、このノリである。
悠平のクダは右から左へ聞き流され、団員は思い思いのプレゼントを風花へ手渡した。
「風花、前にこれ欲しがってたよね?盗っといた!」
梨々華が渡してきたのは、キラキラ輝くイヤリング。
「わぁ〜、素敵なイヤリング!ありがとーっ」
さっそく耳につける風花を見て、他の女の子たちも盛り上がる。
「似合う〜。可愛いよ、風花」「ね、それつけて休日遊びにいくっての、どぉ?」
「あはは、そうしてほしいけど見つかっちゃったらアウトだよ」と梨々華が笑い、風花も頷いた。
「そうだね。じゃあ宝箱に入れて眺めとこっと」
「でた〜、風花の宝箱!そろそろパンパンじゃないの?それ」と樽斗にからかわれ、すかさず本人が否定する。
「三個目盗ってきたから大丈夫だもん」
なんとなくおかしな会話だなと思いつつも、新参の龍輔は口を挟むことなく皆の会話を流し聴く。
皆の用意したプレゼントは、貴金属やらファンシーな雑貨やら可愛い縫いぐるみやらとバラエティーに富んでいる。
貧乏怪盗団だと悠平は謙遜していたが、皆の懐は裕福なのではないか。
去年、風花の誕生日に贈ったドレスの反応はイマイチで、龍輔は失敗したと感じた。
だから、今年は方向性を変えてみた。これならバッチリ、誰とも被らない。
「風花、これ、大事にしてね。帰りに転んじゃったから、ちょっと汚れちゃったけど」
汚れたネックレスを洗いもせず他人のプレゼントにするとは、とんでもない奴だ。
仲間の呆れた非常識っぷりに、龍輔は内心目を丸くする。
「いいよ、いいよ、これくらいなら汚れのうちに入らないって!」
対して、風花の太っ腹なこと。
側面で目立つ汚れだというのに、お構いなしだ。
鎖でぶらさがった青い宝石は彼女の胸元でキラキラ輝いて、これで去年渡したドレスを着てくれれば一層映えたに違いない。
そう、誕生日に着てほしくてドレスを贈ったってのに、風花には意図が伝わらなかったようだ。
「さぁ、そろそろケーキの登場よ!皆、席について」
パンパン手を叩いて、莉子が皆を呼び寄せる。
「悠平、早く早く、ケーキ持ってきて!」
興奮する子供たちを手で宥めながら、悠平は龍輔を振り仰ぐ。
「おう、今年のケーキは趣を変えて手作りだ。心して食えよ?」
「えー!?まさか、悠平が焼いたの?不安しかないんだけど!」と大げさに騒ぎ立てる樽斗や、「ちゃんと食べられるもの作ったんでしょうね!?」と金切り声をあげる麻衣子を手でマァマァと押し留め、悠平が言い直した。
「俺が焼いたんじゃねぇから安心しろ。焼いたのは、ホレ、そこの龍輔だ」
「えー!?」と、これにも子供たちは大合唱。
だって去年入ったばかりで、まだよく性格や素性の判らない新入りが作ったと言われても。
皆の注目を一身に浴びて、龍輔が両手に盆を抱えて持ってきた。
「ほいよ、なかなかの自信作だ。味わって食ってくれよ」
先に切り分けておいたのか盆の上には人数分のケーキが個別の皿に乗っていた。
全体的に真っ茶色、茶色のスポンジ上下の間に挟まっているのは白いクリームで、上に乗るのはチェリーの砂糖漬けだろうか。
これまで皆が一度も食べたことのない、上品な見た目のケーキだ。
皆が盗ってこられるケーキといえば、おっさんが一人で番しているような警備の薄い店じゃないと無理だ。
そして、そうした店で売られているのは大抵素朴な作りのホワイトケーキで、上に乗っかるのも摘みたての苺がせいぜい。
お上品でリッチなケーキを売る店は大通りの中ほどにあり、常に警官が駐在している上、開いているのが昼間だけとあっては、活動時間が夜メインの怪盗団には盗みにくい。
しかも悠平は"龍輔の手作り"だと言った。盗んだのではなく。
こんなケーキ、実際に食べてみなきゃ味だって判るまい。
龍輔が自分たちと同じ貧乏人ではなかった衝撃に、子供たちはポカンと呆けるばかり。
「なによ、これ!こんな上品で高そうなケーキを知っている裕福な自分の幸せ自慢ってわけ!?」
一番最初にキレたのは風花だった。
だが、龍輔が何か言うより早く悠平が割り込む。
「いいじゃねぇか、幸せ自慢。風花、おめぇの為に自腹切って焼いてくれたんだぜ?こいつぁ最高のプレゼントじゃねぇか。食わなきゃ損損。ほら、おめぇらも食え食え」
「自腹?えーっ、もしかして材料も自腹なの!?ってか、うまーい!甘くておいしい!」
樽斗は驚きながらもパクパク食べている。
それを見て他の皆も食べ始めて甘いだの美味しいだのと口々に感想を騒がれては、風花も食べないわけにはいかず。
否、見た瞬間から食べたい欲を抑えきれずにいた。
「こんな綺麗なケーキを手作りできるとか龍輔、有能すぎない?すごすぎない?」
「ねー、あたしの母さんだって作れなかったのに!やば、何個でも入りそう!」
女の子たちがキャアキャア騒ぐ横で自分も一口食べて、「何これ、新食感……ほろっと苦くて甘い」と莉子は感動に震える。
「そう、一瞬苦いんだけど甘いんだよ!何使ってんだろ?初めて食べたから全然わかんねぇ」と隣で騒ぐ樽斗に答えたのは、作った当人だ。
「カカオだ。大通りの食材屋あるだろ、珍しい香薬を売っている。あそこで買った」
「えー、なんでそんなの知って、つーか大通りに、そんな店あったんだ!?よーし、チェックチェック」
食事中だというのにメモを取り始める少年を横目に、龍輔は、それとなく風花の様子を窺う。
幸せ自慢だとキレていた。子供の小遣いで買える程度のケーキを見て。
怪盗団のメンバーが貧乏家庭出身ないし孤児だというのは、悠平から事前に聞いている。
ただ貧乏の度合いが、どれほどなのかが判らなかった。中流家庭で育った龍輔には。
また失敗してしまった。結構、頑張って作ったんだけどな。
彼女の心を掴むプレゼントを考えるのは難しい。皆のように無難なアクセサリーにするべきだったか。
等と、しょんぼりする龍輔の目に映ったのは、チョコレートケーキを口いっぱいに頬張って感動に打ち震える風花の姿であった。
「はふぅ、おいひぃ……こんな美味しいケーキ食べたの、人生はじめて……」
なんと、感動のあまりか涙まで。
「ねー、美味しいよね!いつものホワイトケーキも美味しいんだけど、やっぱ初めては違うよね!」
「しかも手作りだし。手作りケーキって作れる人がいないと食べられないんだから、超レアだよ!!」
「そうだよ、こんなのフツーに買ったら全財産飛んじゃうんじゃないの!?手作りバンザーイ、だよね」
作る人がいなければ手作りケーキを食べられないなんて、そんな当たり前の常識を新発見の如く騒ぎたてている。
龍輔は皆の喜びをポカーンと眺めた。
こちらが当たり前だと思っていたことは、当たり前ではなかったのだ。家が貧乏だと。
しかしケーキをありがたがる割に、風花へのプレゼントは高価なものばかりだった。この違和感は一体。
ふと、口の周りをクリームでベタベタにした風花と目があう。
「……あ、ありがとね。さっきは罵ってゴメン。美味しかったわよ、今年のプレゼント」
不貞腐れられるかと思いきや、まさかのデレ。しかも頬を染めて可愛い顔アンド、謝罪のおまけ付き。
こんな不意打ち、予想していなかっただけに龍輔の心臓は飛び跳ねまくりだ。
いや、この反応が見たくて作ったケーキだけども、本当に見られるとは思っていなかったので!
樽斗に「やったじゃん、龍輔!」と肩を叩いて祝福されて、龍輔が何か気の利いたプロポーズのセリフを探す間に、同じくケーキを食べ終えた誉が風花の目の前に小箱を置いた。
「これ、やる。ブローチだ」
「やったー!誉ちゃんからのプレゼント、今年も大事にするね!」
誉には抱きつくほどの大サービスで、またまた龍輔は目を丸くする。
ブローチは純白に輝く宝石が嵌められて、貧乏人はおろか中流家庭でも買えそうにないのだが。
皆の懐具合が貧乏なのか裕福なのかが判らず、龍輔は一人首をひねる。
後日、皆の誕生日プレゼントが全て盗品だったと彼が知ったのは、何気ない雑談での誉の一言であった――
おしまい